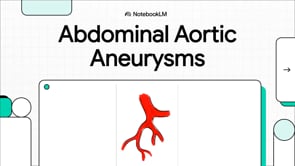乳がんホルモン療法の世界的権威であるマーク・リップマン医学博士が、内分泌療法の歴史と最新の知見について解説します。ホルモン依存性乳がんが初めて確認されたのは数世紀前にさかのぼると述べ、外科的切除から現代的な薬物療法への発展の経緯を詳説。内分泌療法は乳がん治療における最大のブレークスルーであると強調し、これらの治療法が死亡率を大幅に低下させ、乳がんの予防すら可能にしている点を指摘します。
乳がんホルモン療法:歴史・進歩・予防
セクションへ移動
ホルモン療法の初期の歴史
乳がんにおけるホルモンの関与は、何世紀にもわたって観察されてきました。マーク・リップマン医師(医学博士)は、17世紀イタリアのヴェローナで実施された疫学研究を引用しています。これらの研究では、修道女と一般女性との間で乳がん発生率に差があることが示されました。最初の古典的内分泌療法は19世紀後半に登場し、外科医が閉経前の乳がん患者に対して卵巣摘出術(卵巣切除)を実施。リップマン医師は、この処置により一部の患者が著しい客観的反応を示したと述べています。
内分泌学における科学的ブレークスルー
ホルモン療法が真の科学として発展するには長い年月を要しました。最大の障壁は、ホルモン濃度を測定する手段がなかったことです。リップマン医師によれば、この状況は1960年代初頭に一変。ラジオイムノアッセイとラジオレセプターアッセイの発明が決定的な突破口となり、極めて低濃度のステロイドホルモンやペプチドホルモンの測定が可能になりました。これにより内分泌学は真の科学へと発展し、ホルモンのフィードバック機構が解明され、乳がんがホルモン依存性疾患であることが容易に理解できるようになりました。
リップマン医師はエストロゲンと成長の関係について重要な洞察を示しています。アントン・チトフ医師(医学博士)に対し、男性にエストロゲンを投与すると乳房が発達すると説明。ただし、この成長には自然な限界があります。一方、乳がん細胞はエストロゲンの刺激を受けると増殖を抑制する機能を失い、無制限に成長を続けてしまいます。このメカニズムが1940年代に明らかとなり、科学的な内分泌療法への道が開かれました。
外科的内分泌療法の進化
初期の内分泌療法は、ホルモン産生器官の外科的切除に焦点が置かれていました。卵巣摘出術は閉経前患者の主要な治療法として継続して用いられ、副腎摘出術(副腎切除)も実施されました。リップマン医師は、副腎切除後には生命維持に不可欠なグルココルチコイドの補充が必要であったと指摘。副腎は乳がんの成長を促進するエストロゲンの間接的な供給源であったためです。
もう一つの主要な外科的処置として下垂体摘出術(下垂体切除)があり、リップマン医師はこの手術によりゴナドトロピンとACTH(副腎皮質刺激ホルモン)が除去され、ホルモンレベルが低下して乳がんの退縮がもたらされたと説明しています。薬物療法が開発される以前の長年にわたり、これらの切除手術は広く実施され、高い成功率を収めました。
抗エストロゲン薬の開発
1970年代から1980年代にかけての大きな進歩は、外科的手術から離れる方向にありました。目標は、切除を伴わずに同等の内分泌効果を達成することであり、これが抗エストロゲン薬の開発へとつながりました。リップマン医師は、これらの薬剤がエストロゲンの作用を阻害することで機能し、適切な患者に投与されれば乳がんの退縮を引き起こすと説明しています。
この薬物療法への転換は画期的な進歩でした。大手術に伴うリスクや合併症なしに効果的な治療が可能となり、リップマン医師とチトフ医師の対話は、これが腫瘍学における重要な転換点であったことを強調しています。
早期がんに対する内分泌療法
治療における重要な進化は、内分泌療法がより早期の病期に適用されるようになったことです。転移性乳がんに有効であった治療法が、補助療法(アジュバント療法)として進展。乳房切除術や乳房温存術などの初期治療後に実施され、再発予防を目的としました。リップマン医師は、30~40年前に開始された臨床試験のデータが現在も分析中であると述べています。
これらの試験は生存率の著しい改善をもたらし、リップマン医師は、本来なら死亡していたであろう多くの患者が治癒したと強調。ホルモン療法の適切な使用は、乳がん治療における最大の進歩であり、死亡率の驚異的な低下をもたらしたと評価しています。
乳がん予防療法
最新の進歩は、内分泌療法を予防に応用することです。リップマン医師は、その有効性を支持する説得力のあるデータを提示。エストロゲンの作用を阻害する治療を5年間行うことで、全乳がんの60~75%を予防できると説明し、データが明確かつ強力であると述べています。
しかし、こうした強力なエビデンスにもかかわらず、リップマン医師は重大な課題を指摘。これらの予防療法は本来あるべきほど広く普及しておらず、公衆衛生上の大きな機会損失となっています。広範な導入により、多数の乳がん発症を防ぐことができたはずです。チトフ医師は、これらの知見の重要性を強調するため、リップマン医師と議論を交わしています。
全文書き起こし
アントン・チトフ, MD(医学博士): リップマン教授、あなたはホルモン依存性乳がんの最初のモデルを構築され、以来ずっとホルモン療法の最前線でご活躍されています。ホルモン療法を用いた乳がん治療の歴史と現状について、概要を説明していただけますか?
マーク・リップマン, MD(医学博士): はい。ホルモンが乳がんに関与していることは約300年前から認識されていました。17世紀のイタリア、ヴェローナで実施された疫学研究では、修道女と一般女性の間で乳がん発生率に差があることが示され、これは乳房の使用の有無に関連すると正しく帰属されました。
内分泌療法の最初の古典的なアプローチは19世紀後半に始まり、卵巣の除去が乳がんに有益な効果をもたらす可能性が検討されました。閉経前の女性患者に対する卵巣摘出術は、実際に一部の患者で著しい客観的反応をもたらし、非常に満足のいく結果となりました。
しかし、その科学的基盤が明らかになるまでには長い時間がかかりました。当時はホルモンの作用機序が不明であっただけでなく、測定技術も未発達でした。1960年代初頭のラジオイムノアッセイとラジオレセプターアッセイの発明により、状況は一変。極めて低濃度のステロイドホルモンやペプチドホルモンの測定が可能となり、内分泌学は真の科学へと発展しました。
ホルモンのフィードバック機構が解明され、乳がんがホルモン依存性疾患であることが容易に理解できるようになりました。思春期の少女ではエストロゲンレベルの上昇に伴い乳房が発達すること、また男性にエストロゲンを投与すると乳房が成長することは既知でしたが、重要な観察は、エストロゲンによる成長には限界があるということです。
女性は思春期に乳房を発達させますが、その後数十年間エストロゲンに曝露されても乳房は特に変化しません。一方、乳がん細胞はエストロゲンへの反応性を保持しているものの、増殖を抑制する機能を失っているため、エストロゲンの刺激がある限り成長と転移を続けてしまいます。
この理解に基づき、1940年代には卵巣摘出を含む科学的な内分泌療法の開発が進みました。副腎はエストロゲンの間接的な供給源であるため、副腎摘出術も実施されましたが、生命維持のためグルココルチコイドの補充が必要でした。
長年にわたり、下垂体摘出術も一般的かつ成功裡に実施され、ゴナドトロピンとACTH(副腎皮質刺激ホルモン)の除去によりホルモンレベルが低下し、乳がんの退縮がもたらされました。
1970年代から1980年代の主要な進歩は、外科的切除を伴わずに同等の内分泌効果を達成する方法の開発でした。一般に抗エストロゲンと呼ばれる薬剤が開発され、エストロゲンの作用を阻害することで適切な患者に投与されれば乳がんの退縮を引き起こします。
腫瘍学において一般的なパターンとして、進行した病態(転移性がん)に対して有効であった治療法が、より早期の病期へと進展しました。乳がんの内分泌療法も同様で、最初は転移性がん患者に使用され、後に原発性乳がんに対する乳房切除術や乳房温存術後の再発予防として応用されるようになりました。
これらの臨床試験は30~40年経った現在も分析中ですが、生存率の著しい改善をもたらしました。実際、本来なら死亡していたであろう多くの患者が治癒し、死亡率の驚異的な低下は、局所療法時のホルモン療法(場合により化学療法)の適切な使用による乳がん治療最大の進歩と言えます。
近年では、これらの内分泌療法が乳がん予防にも有効であることが明らかになってきました。ただし、これらの治療は本来あるべきほど広くは使用されていません。
エストロゲンの作用を阻害する治療を5年間行うことで、全乳がんの60~75%を予防できるというデータは明確かつ説得力があります。
マーク・リップマン, MD(医学博士): しかし残念ながら、これらの療法は本来あるべきほど広くは使用されていません。