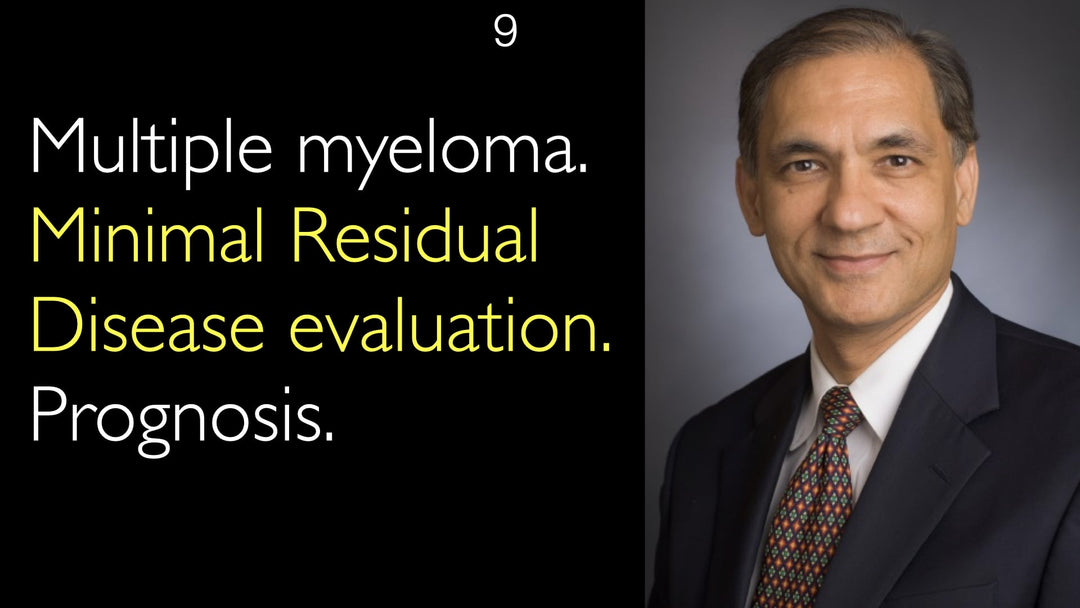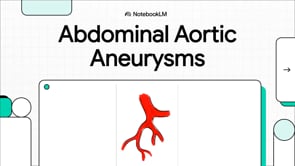多発性骨髄腫の世界的権威であるNikhil Munshi医師(医学博士)が、最小残存病変(MRD)評価が極めて重要な予後因子である理由を解説します。MRD検査における最新手法である次世代シークエンシング(NGS)と次世代フローサイトメトリーの詳細を解説し、最適な予後判断に必要な感度レベルを明らかにします。新規診断例・再発例を問わず、骨髄腫治療の主要な目標はMRD陰性状態の達成にあります。
多発性骨髄腫における微小残存病変:検査法と予後への意義
セクションへ移動
多発性骨髄腫におけるMRDの予後的意義
治療への反応性は、多発性骨髄腫患者の重要な予後因子です。Nikhil Munshi医師(医学博士)は、微小残存病変(Minimal Residual Disease: MRD)の測定が現在きわめて重要であると強調しています。MRD評価は臨床研究における患者の転帰に直接影響を与え、現在では骨髄腫治療における治療方針決定の指標としても用いられています。
次世代シーケンシングによるMRD検査
次世代シーケンシング(Next-Generation Sequencing: NGS)は、微小残存病変を評価する主要な手法の一つです。NGSは、治療後に残存する骨髄腫細胞を高感度で検出する手法を提供します。Nikhil Munshi医師(医学博士)によれば、このシーケンシング技術はがん細胞集団の詳細な解析を可能にします。医師は自身の経験や検査環境に応じてこの手法を選択することができます。
次世代フローサイトメトリー法
次世代フローサイトメトリーは、多発性骨髄腫におけるMRD評価のもう一つの主要な手法です。この技術は、残存病変の検出においてシーケンシング法と同等の感度を実現します。Nikhil Munshi医師(医学博士)は、次世代シーケンシング(NGS)と次世代フローサイトメトリーの性能が非常に類似していると指摘しています。手法の選択は、医師の判断や施設のリソースに依存します。
最適なMRD感度レベルと検出
検出感度の深さは、多発性骨髄腫のMRD検査において重要な要素です。望ましい感度レベルは10⁻⁶であり、これは100万個の正常細胞の中に1個のがん細胞を検出できることを意味します。Nikhil Munshi医師(医学博士)は、技術的な制約からこの理想的な感度を達成できない場合もあると述べています。一般的な臨床現場では、10⁻⁵(10万細胞中に1個の腫瘍細胞を検出可能)の感度が予後評価において許容されるとされています。
治療目標としてのMRD陰性化の達成
新たに診断された多発性骨髄腫患者における主要な治療目標は、MRD陰性状態を達成することです。Nikhil Munshi医師(医学博士)は、この目標が再発した骨髄腫患者にも同様に適用できることを示す新たなデータを強調しています。この目標は、患者の治療反応を評価し、治療期間を決定する上で重要な指針となります。Anton Titov医師(医学博士)との対談で、Munshi医師はMRDの状態が患者への治療量や期間を決める上で有用な情報を提供すると強調しました。
全文書き起こし
Nikhil Munshi医師(医学博士): 治療への反応性は、多発性骨髄腫の主要な予後因子です。多発性骨髄腫患者の微小残存病変(Minimal Residual Disease: MRD)を評価する最新技術の現状と、最良の予後をもたらすMRDレベルについて教えてください。
先ほども触れたように、微小残存病変の測定は、さまざまな研究の転帰を評価する上で非常に重要であるだけでなく、治療方針を決定する指標としても用いられています。
主に二つの手法があります:一つは次世代シーケンシング(Next-Generation Sequencing: NGS)と呼ばれるシーケンシングベースの手法、もう一つは次世代フローサイトメトリーです。両手法の性能は非常に類似しており、医師が使い慣れた手法を選択することができます。
重要な点は、お尋ねの通り、検出の感度の深さです。標準的には10⁻⁶の感度、つまり100万細胞中に1細胞を検出できるレベルが望ましいとされています。
しかし、技術的な理由などから、このレベルを達成できない場合もあることを認識しておく必要があります。そのため、一般的な臨床現場では10⁻⁵、つまり10万細胞中に1個の腫瘍細胞を検出できるレベルが許容基準となります。
この点を常に意識することが重要だと考えています。目標は、新規診断症例において患者をMRD陰性の状態に導くことです。
再発した骨髄腫患者を治療する際にも同様の目標が適用可能であることを示す新たなデータも出てきています。したがって、患者の治療においては常にこれを意識し、治療への反応を評価するとともに、治療の量と期間を決定する必要があります。