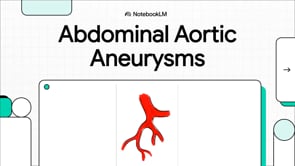2つの大規模臨床試験の統合解析により、月1回の皮下投与で用いるオファツムマブ(ケシンプタ)が、新たに診断された多発性硬化症患者において、経口薬のテリフルノミド(オーバジオ)と比較して、統計的に有意な優位性を示すことが確認されました。オファツムマブは再発率を50%減少させ、障害の進行を46%抑制し、MRI上の病変活動に対しても優れた抑制効果を発揮しました。さらに、許容範囲内の安全性プロファイルを維持しており、これらの結果から、新規診断MS患者に対する第一選択治療としてオファツムマブを考慮する強力な根拠が得られました。
新規診断多発性硬化症患者におけるオファツムマブのテリフルノミドに対する優位性
目次
- はじめに:多発性硬化症における早期治療の重要性
- 研究方法:試験の実施方法
- 参加者特性:試験対象者の特徴
- 主要な結果:詳細な数値結果
- 安全性プロファイル:治療に伴う副作用と忍容性
- 臨床的意義:患者にとっての意味
- 試験の限界:本研究で証明できなかった点
- 推奨事項:患者向け実践的なアドバイス
- 出典情報
はじめに:多発性硬化症における早期治療の重要性
多発性硬化症(MS)は、若年成人における中枢神経系(脳および脊髄)の最も一般的な慢性炎症性・神経変性疾患であり、非外傷性障害の主要な原因となっています。再発型MS(RMS)患者では、障害の蓄積は段階的に起こると考えられてきました。まず再発からの回復不良によって生じ、その後は再発とは無関係に進行するとされていました。
しかし、近年の研究により、不完全な回復を伴う再発と再発活動とは無関係な進行(PIRA)の両方が、疾患発症時から障害に寄与していることが明らかになっています。特に、進行期MSにおける神経変性と不可逆的な進行の主要な駆動因子である神経軸索損失は、早期RMSにおいて既に有意である可能性が示されています。
若年RMS患者は通常、より高い臨床的およびMRI上の疾患活動性を示し、より顕著な急性軸索損傷を伴います。神経細胞および脳容積の減少は疾患経過の早期から始まり、高い障害レベル、高い病変負荷、および低い脳容積はMSの予後不良と関連しています。
疾患修飾療法(DMT)のMS障害悪化への効果は年齢依存的であり、若年患者および疾患経過の早期段階にある患者が最大の利益を得られます。これにより、障害の蓄積を遅らせることができる高効率DMTによる早期治療が不可欠となります。ただし、これらのより効果的な治療による早期介入を妨げる障壁がしばしば存在します。
研究方法:試験の実施方法
本解析は、第III相ASCLEPIOS IおよびII試験からのデータを検討しました。これらの試験は、再発型多発性硬化症の参加者を対象に同時に実施された、同一デザインの無作為化二重盲検二重ダミー活性薬対照多施設共同試験です。試験はClinicalTrials.gov(NCT02792218およびNCT02792231)に登録されています。
参加者は無作為に(1:1比率で)以下のいずれかの治療を受けるよう割り付けられました:
- オファツムマブ:20mgを4週間ごとに皮下投与(初回投与として1日目、7日目、14日目に20mg投与後、4週目から開始)
- テリフルノミド:14mgを1日1回経口投与
治療は最長30ヶ月間継続されました。解析は特にプロトコルで定義された最近診断され治療未経験(RDTN)のサブ集団に焦点を当てました。これはスクリーニング前36ヶ月以内にRMSと診断され、事前にいかなる疾患修飾療法による治療も受けていなかった参加者です。
研究者らは治療効果を評価するために複数のエンドポイントを解析しました:
- 年間再発率(ARR):1年に標準化された確認済みMS再発数
- 拡大障害ステータススケール(EDSS)の変化により測定された3ヶ月および6ヶ月時の確認済み障害悪化(CDW)
- 3ヶ月および6ヶ月時の再発活動とは無関係な進行(PIRA)
- MRI測定値:ガドリニウム増強T1病変、新規/増大T2病変、脳容積変化
- 疾患活動性の証拠なし(NEDA-3):再発なし、障害悪化なし、MRI活動性なし
- ニューロフィラメント軽鎖(NfL)濃度:神経損傷のバイオマーカー
- 安全性アウトカム:有害事象、重篤な有害事象、および中止率
参加者特性:試験対象者の特徴
全体のASCLEPIOS試験の1,882名の参加者のうち、615名(32.7%)が最近診断され治療未経験のMS患者の基準を満たしました。これらの参加者は以下のように分けられました:
- オファツムマブ群:314名
- テリフルノミド群:301名
RDTN参加者は非常に最近MSと診断されており、オファツムマブ患者では中央値0.35年、テリフルノミド患者では0.36年で、両群とも診断からの範囲は0.1~2.9年でした。
主要な人口統計学的および疾患特性は以下の通りでした:
- 平均年齢:36.8歳(オファツムマブ)対35.7歳(テリフルノミド)
- 性別:女性69.1%(オファツムマブ)対64.8%(テリフルノミド)
- MSタイプ:両群とも99%が再発寛解型MS(RRMS)
- 平均EDSSスコア:2.30(オファツムマブ)対2.28(テリフルノミド)—軽度の障害を示唆
- ベースライン時点でオファツムマブ患者の44.9%、テリフルノミド患者の43.2%にガドリニウム増強病変が認められました
試験全体の集団と比較して、RDTN参加者は予想通り、より若年で障害スコアが低く、総T2病変容積も低いことが示されました。
治療曝露は相当なものでした:
- 中央値期間:1.7年(オファツムマブ)対1.6年(テリフルノミド)
- 患者の90%以上が1年以上治療を受けました
- 25%以上が2年以上治療を受けました
遵守率は極めて高く、オファツムマブで98.8%、テリフルノミドで98.9%であり、完全遵守はそれぞれ54.5%および58.5%でした。
主要な結果:詳細な数値結果
結果は、MSの疾患活動性および進行の複数の測定値において、オファツムマブに有意な優位性があることを示しました。
再発減少: オファツムマブはテリフルノミドと比較して年間再発率を50%減少させました:
- ARR:0.09(オファツムマブ)対0.18(テリフルノミド)
- 率比:0.50(95% CI:0.33, 0.74)
- 統計的有意性:p < 0.001
障害進行: オファツムマブは確認済み障害悪化を有意に遅延させました:
- 3ヶ月CDW:38%のリスク減少(HR:0.62;95% CI:0.37, 1.03;p = 0.065)
- 6ヶ月CDW:46%のリスク減少(HR:0.54;95% CI:0.30, 0.98;p = 0.044)
全障害悪化イベントの半数以上が再発なし(再発活動とは無関係な進行)で発生しました:
- 3mCDWイベント:13/24(オファツムマブ)対20/37(テリフルノミド)がPIRAでした
- 6mCDWイベント:9/17(オファツムマブ)対17/30(テリフルノミド)がPIRAでした
PIRA(再発活動とは無関係な進行): 確認済み再発のない患者において:
- 3mPIRA:6.6%(オファツムマブ)対9.1%(テリフルノミド);HR:0.55(0.27, 1.11);p = 0.096
- 6mPIRA:3.6%(オファツムマブ)対7.7%(テリフルノミド);HR:0.44(0.20, 1.00);p = 0.049
MRIアウトカム: オファツムマブはMRI上の疾患活動性を劇的に減少させました:
- ガドリニウム増強T1病変:95%減少(1回のスキャンあたり0.02対0.39病変;率比:0.05;p < 0.001)
- 新規/増大T2病変:82%減少(年間0.86対4.78病変;率比:0.18;p < 0.001)
- 脳容積減少:群間で有意差なし(年間-0.30%対-0.31%;p = 0.9)
疾患活動性の証拠なし(NEDA-3): オファツムマブはNEDA-3(再発なし、障害悪化なし、MRI活動性なし)の達成オッズを有意に増加させました:
- 1年目:47.0%対24.7%(オッズ比:3.31;p < 0.001)
- 2年目:92.1%対46.8%(オッズ比:14.68;p < 0.001)
- 全体(0-24ヶ月):44.6%対17.7%(オッズ比:4.63;p < 0.001)
ニューロフィラメント軽鎖(バイオマーカー): 血清NfL濃度(神経損傷のマーカー)はオファツムマブで有意に低くなりました:
- 3ヶ月時:8.72対9.13 pg/mL(有意差なし)
- 12ヶ月時:6.60対8.61 pg/mL(24%減少;p < 0.001)
- 24ヶ月時:6.47対8.10 pg/mL(20%減少;p < 0.001)
安全性プロファイル:治療に伴う副作用と忍容性
最近診断され治療未経験の参加者における安全性所見は管理可能であり、全体のASCLEPIOS集団と一致していました。
全般的な有害事象:
- オファツムマブ:参加者の84.7%が何らかの有害事象を経験
- テリフルノミド:参加者の86.0%が何らかの有害事象を経験
一般的な有害事象(患者の≥10%で発生):
オファツムマブ:
- 鼻咽頭炎(風邪)
- 注射関連全身反応
- 頭痛
- 上気道感染症
テリフルノミド:
- 鼻咽頭炎
- 脱毛症
- 上気道感染症
- 注射関連全身反応(プラセボ注射から)
- 頭痛
- 疲労
重篤な有害事象:
- オファツムマブ:22名(7.0%)
- テリフルノミド:16名(5.3%)
- いずれの治療群でも死亡例は発生せず
注射関連反応:
- 注射関連全身反応:20.1%(オファツムマブ)対15.0%(テリフルノミド—プラセボ注射を受けた)
- 注射部位反応:14.0%(オファツムマブ)対7.0%(テリフルノミド)
- 初回注射後、全身反応の頻度は群間で類似していました
臨床的意義:患者にとっての意味
本解析は、最近診断され治療未経験の多発性硬化症患者において、オファツムマブがテリフルノミドと比較して優れた有効性を提供するという説得力のあるエビデンスを提供します。50%の再発率減少、46%の障害進行減少、および疾患活動性の証拠なしの達成率の有意な高さは、実質的な臨床的利点を示しています。
新規診断MS患者にとって、これらの知見は、オファツムマブのような高効率治療を開始することで、初期から疾患活動性をより効果的に制御し、より良い長期的アウトカムが得られる可能性を示唆しています。再発活動とは無関係な進行の有意な減少は特に重要です。なぜなら、このタイプの障害蓄積は明らかな再発なしに静かに起こるからです。
管理可能な安全性プロファイルと前投薬なしの在宅投与の選択肢は、オファツムマブを早期治療の実用的な選択肢としています。試験で観察された高い遵守率は、患者が一般的に治療をよく耐容していることを示唆しています。
MRI病変の劇的減少(ガドリニウム増強病変の95%減少および新規T2病変の82%減少)は、炎症活動性の強力な抑制を示しており、時間の経過とともに脳組織のより良い保存につながる可能性があります。
試験の限界:本研究で証明できなかった点
本解析は貴重な知見を提供しますが、いくつかの限界を考慮すべきです:
これは大規模試験からの参加者サブセットの事後解析であり、事前に指定された主要エンドポイントではありません。知見は決定的ではなく探索的なものとして解釈されるべきです。
中央値約1.7年の研究期間は、通常数十年かけて進行する多発性硬化症(MS)の長期的な障害転帰を評価するには比較的短期間です。障害の進行に対する完全な影響を理解するには、より長期的な追跡調査が必要です。
比較対象はテリフルノミドに限定されており、他の高効力疾患修飾療法(DMT)とは比較されていません。そのため、オファツムマブが全ての第一選択治療オプションと比較してどのような位置づけにあるかは示されていません。
解析は臨床的転帰とMRI所見に焦点を当てていますが、患者報告転帰や生活の質(QOL)評価は含まれておらず、これらは患者視点におけるMS治療において重要な側面です。
最後に、RDTN(新規診断未治療)集団は重要なサブグループではありますが、結果が全てのMS患者集団、特に罹病期間が長い患者や既往治療歴のある患者に一般化できるとは限りません。
推奨事項:患者のための実践的アドバイス
これらの研究知見に基づき、新規に診断された多発性硬化症(MS)患者は以下を考慮すべきです:
高効力早期治療の検討: 中等度効力治療からの段階的エスカレーションではなく、オファツムマブのような高効力療法で治療を開始することの潜在的利点について、神経専門医と詳細に議論してください。エビデンスは、このアプローチが初期から疾患活動性をより良く抑制する可能性を示唆しています。
治療オプションの理解: 異なる投与方法について学びましょう——オファツムマブは月1回の皮下注射で自宅で自己投与可能であり、テリフルノミドは経口薬を毎日内服します。自身の生活様式と希望に最も合うアプローチを考慮してください。
副作用のモニタリング: 各薬剤の潜在的な副作用を認識してください。オファツムマブは投与関連反応(特に治療初期)を、テリフルノミドは脱毛を引き起こす可能性があります。懸念事項は医療チームに報告してください。
定期的なモニタリング: どの治療を選択しても、神経専門医が推奨する定期的な経過観察とMRIモニタリングを遵守してください。疾患活動性の早期発見は、適時の治療調整を可能にします。
共有意思決定: 治療の有効性と安全性に関する最新のエビデンスを考慮しつつ、自身の目標、価値観、生活様式に沿った治療決定を下すため、医療チームと協働してください。
出典情報
原論文タイトル: "Efficacy and safety of ofatumumab in recently diagnosed, treatment-naive patients with multiple sclerosis: Results from ASCLEPIOS I and II"
著者: Jutta Gärtner, Stephen L Hauser, Amit Bar-Or, Xavier Montalban, Jeffrey A Cohen, Anne H Cross, Kumaran Deiva, Habib Ganjgahi, Dieter A Häring, Bingbing Li, Ratnakar Pingili, Krishnan Ramanathan, Wendy Su, Roman Willi, Bernd Kieseier, Ludwig Kappos
掲載誌: Multiple Sclerosis Journal, 2022, Vol. 28(10) 1562–1575
注記: 本患者向け記事は、ClinicalTrials.gov(NCT02792218およびNCT02792231)に登録されたASCLEPIOS IおよびII臨床試験からの査読付き研究に基づいています。