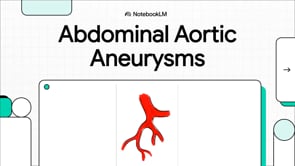本総説では、過去20年間の幹細胞研究における主要な進展を概観し、現在科学者が成体細胞をあらゆる細胞種へ分化可能な多能性幹細胞へと再プログラム化する手法を解説する。胚性幹細胞、極小胚様幹細胞、核移植幹細胞、再プログラム化幹細胞、成体幹細胞という5つの主要な幹細胞タイプを網羅し、それぞれの細胞源と臨床応用の可能性について詳述する。主な進展には、ウイルス・RNA・化学物質を用いた改良型再プログラム化法、動物由来成分を含まない培養システムの開発、移植可能な組織や臓器の作出につながる3Dバイオプリンティング技術の台頭が含まれる。
幹細胞研究の最新動向:実験室から臨床応用へ
目次
はじめに
幹細胞研究は過去20年間で革命的な進展を遂げ、特にこの10年で飛躍的に加速した。この分野は1961年、カナダの研究者James A. Till博士とErnest A. McCulloch博士がマウス骨髄中に多様な細胞へ分化可能な幹細胞を初めて発見し、体内のあらゆる細胞種へなり得る多能性幹細胞(PSCs)の概念を確立したことに端を発する。
幾つかの画期的な成果が達成された:1996年には体細胞核移植(SCNT)により羊のドリーがクローン化され、1998年に初のヒト胚性幹細胞(hESCs)が単離され、2006年にはわずか4つの転写因子で成体細胞を再プログラム化し誘導多能性幹細胞(iPSCs)が作出された。これらの発見の重要性は、成熟細胞が多能性状態へ再プログラム化可能であることを示した功績により、山中伸弥とジョン・ガードンが2012年にノーベル賞を受賞したことで広く認められた。
系統的レビューを通じて、研究者らは胚性幹細胞(ESCs)、極小胚様幹細胞(VSELs)、核移植幹細胞(NTSCs)、再プログラム化幹細胞(RSCs)、成体幹細胞という5つの主要な幹細胞カテゴリーを同定した。各タイプは臨床応用において独自の利点と課題を有する。NTSCsのみが完全な個体の作出(2018年中国におけるサルの例)に用いられたのに対し、他のタイプは組織や臓器の生成に応用されている。
幹細胞、特にESCsとiPSCsは、再生・移植医療、疾患モデリング、創薬スクリーニング、ヒト発生生物学の4領域で極めて大きな可能性を秘める。この分野は基礎研究から臨床応用へと発展を続けているが、特にiPSC再プログラム化技術が比較的新しいため、細胞増殖と分化制御に関する課題が残されている。
多能性幹細胞の細胞源
多能性幹細胞(PSCs)は、自己複製能(増殖能力)と多能性(外胚葉、内胚葉、中胚葉の三胚葉に由来する特殊化細胞へ分化する能力)という二つの必須特性によって定義される。研究者らはマウスモデルにおいて多能性を評価するため、三つの主要なアッセイ法を用いる。
奇形腫形成アッセイは、免疫不全マウスへ細胞を移植後、三胚葉すべてから分化組織が自発的に生成されるかを検証する。キメラ形成アッセイは、幹細胞を初期胚(2N胚盤胞)へ注入し、ドナー細胞が生殖系列へ寄与し機能的な配偶子を生成するか、染色体完全性を保持するかを試験する。四倍体(4N)補完アッセイは、細胞を4N胚へ注入し、胚体外組織系譜への寄与をモニタリングすることで、多能性細胞の個体全体を形成する能力を評価する。
胚性幹細胞(ESCs)
ヒト胚性幹細胞(hESCs)は、初期胚盤胞(受精後4-5日)から、胚盤胞を破壊するか、または後期組織(妊娠3ヶ月齢まで)を採取することで回収される。研究応用に用いられた最初の幹細胞であり、現在も臨床試験(clinicaltrials.govで追跡)で広く使用されている。
hESCsは多能性のゴールドスタンダードとされるが、胚破壊に伴う倫理的懸念や、移植時の免疫拒絶問題を伴う。これらの課題にもかかわらず、hESCsは発生生物学に関する貴重な知見を提供し続け、新たな幹細胞技術の重要な比較対象として機能している。
極小胚様幹細胞(VSELs)
極小胚様幹細胞(VSELs)と呼ばれる新規多能性幹細胞は、2006年の同定以来、注目を集めている。20以上の独立研究室がその存在を確認しているが、有効性に疑問を呈するグループもある。これらの細胞は、多能性マーカーを発現する成体組織中に存在する小型の初期発生幹細胞である。
VSELsの大きさは、マウスで約3-5μm、ヒトで約5-7μm(赤血球よりわずかに小さい)である。SSEA、核内Oct-4A、Nanog、Rex1などのESCsマーカーに加え、StellaやFragilisなどの移動性原始生殖細胞マーカーを発現する。その発生起源は、胚発生中の器官形成における生殖系列の沈着に関連する可能性がある。
2019年に提案されたモデルによれば、VSELsは原始生殖細胞に由来し、間葉系幹細胞(MSCs)、hemangioblasts(造血幹細胞と内皮前駆細胞を含む)、組織 committed stem cellsの三つの運命へ分化する。多能性幹細胞として、VSELsは成体において胚葉を越えた分化が可能である利点を有し、単能性組織 committed stem cellsの代替となり得る。
VSELsは、ESCsの倫理的論争やiPSCsの腫瘍形成リスクといった問題を克服し得る。これら懸念が重大な障壁となる将来の幹細胞研究および臨床応用において、VSELsは特に有望視されている。
核移植幹細胞(NTSCs)
元来1996年に確立された体細胞核移植(SCNT)法は、核移植幹細胞(NTSCs)を生成するために漸進的に進化してきた。このプロセスは、完全に分化した体細胞(線維芽細胞など)からのドナー核を、脱核した卵母細胞(核を除去した卵細胞)へ移植することから始まる。
新しい宿主卵細胞はドナー核の遺伝的再プログラム化を誘導する。単一細胞の培養中における有糸分裂を経て胚盤胞(約100細胞)が形成され、最終的には元の個体とほぼ同一のDNAを有する個体、すなわち核ドナーのクローンを生成する。このプロセスは治療的クローニングと生殖的クローニングの両方を可能とする。
羊のドリー(1996年)は哺乳類初の成功的生殖クローンであった。以来、約20種以上の他の種がクローン化されている。2018年1月、上海の中国人工学者らは、胎児線維芽細胞を用いたSCNTにより2頭の雌アカゲザルのクローン化に成功したと発表した。この方法による霊長類クローン化は初めてである。
クローン化霊長類の作出は、ヒト疾患研究に革命をもたらし得る。遺伝的に均一な非ヒト霊長類は、霊長類生物学および生物医学研究における貴重なモデルとして、疾患機序と薬物ターゲットの研究を助け、遺伝的変動の交絡因子と必要な実験動物数を減少させ得る。この技術はCRISPR-Cas9ゲノム編集と組み合わせることで、パーキンソン病や各種癌などのヒト疾患の遺伝子改変霊長類モデルを作成し得る。
製薬会社は薬物試験のためのクローンサル需要が高い。この見通しを受け、上海は国際利用のためのクローン研究動物を生産する国際霊長類研究センター設立の資金調達を優先している。SCNTは、細胞シート、組織、臓器片だけでなく生体全体を生成できる点で幹細胞アプローチの中で独特であり、基礎研究と臨床応用の両面でESCsやiPSCsに対する生物生理学的利点を有する。
再プログラム化幹細胞(RSCs)
2006年に山中らが初めて誘導多能性幹細胞(iPSCs)を作出して以来、再プログラム化技術は著しく進歩した。これは特に、系統制限転写因子、RNAシグナル修飾、低分子化合物を用いた実験室内(in vitro)および生体内(in vivo)の直接再プログラム化法において顕著である。
これらの直接アプローチはiPSC段階を省略し、神経細胞や運動ニューロンなどの標的細胞系統に近い、誘導神経前駆細胞(iNPCs)のようなより精密な細胞を産生する。再プログラム化幹細胞(RSCs)は、SCNT法を除く、一次細胞の遺伝的シグナルを再プログラム化するあらゆる実験室的方法により派生する。
hESCsに関連する倫理的および免疫原的課題を克服するため、iPSCsは成体体性組織に由来する有望な代替として台頭した。血液、皮膚、尿を含むヒトiPSC源は豊富である。hiPSCsは個々の患者から採取できるため、同一患者へ再移植時(自家移植)に免疫拒絶を回避できる。
研究者らは、尿中に存在する尿細管細胞からhiPSCsを得る方法を開発した。30mLの尿サンプルのみを要するプロトコルは簡便で、比較的迅速、費用効果が高く、普遍的(あらゆる年齢、性別、人種/民族的背景の患者に適用可能)である。全手順は細胞培養2週間と再プログラム化3-4週間のみを含み、優れた分化能を有する高収量のiPSCsを産生する。
センダイウイルスデリバリーシステムにより200mL清潔中間尿サンプルから回収された尿由来iPSCsは、正常な核型(染色体構造)を示し、奇形腫アッセイにおいて三胚葉すべてへ分化する可能性を確認した。尿から単離された細胞のサブポピュレーションは、前駆細胞の特徴であるc-Kit、SSEA4、CD105、CD73、CD91、CD133、CD44マーカーの細胞表面発現を示し、膀胱細胞系統(尿路上皮、平滑肌、内皮および間質)を識別し得るため、有望な代替細胞源となっている。
成体幹細胞
成体幹細胞は、体内の様々な組織中に存在する別の重要な幹細胞カテゴリーを代表する。多能性幹細胞とは異なり、通常は多能性であり、起源組織に特異的な限られた範囲の細胞種へ分化可能である。
一般的な供給源には、骨髄、脂肪組織、歯髄、各種臓器が含まれる。間葉系幹細胞(MSCs)は最も研究が進んでいる成人幹細胞の一つであり、炎症性疾患の治療、組織修復の促進、免疫応答の調節において有望な成果を示している。
多能性幹細胞ほど多様性はないが、成人幹細胞には倫理的懸念が少ない、腫瘍形成リスクが低い、骨髄移植などの確立された臨床応用があるといった利点がある。その全容と作用機序を解明する研究が続けられている。
臨床応用と将来展望
幹細胞研究は、基礎研究、前臨床試験を経て、現在では複数の応用分野で臨床試験が実施される段階に至った。再プログラム化因子の組み合わせ、実験手法、シグナル伝達経路の解明における進歩により、網膜細胞移植および脊髄移植の初の臨床試験が実現した。
この分野では、細胞増殖と分化制御に関する課題への対応が継続されている。研究者らは以下の方法論的テーマを体系的に検討している:ゲノム修飾による多能性誘導、再プログラム化因子を組み込んだ新規ベクターの構築、低分子化合物および遺伝子シグナル伝達経路を用いたiPSC多能性の促進、マイクロRNAによる再プログラム化効率の向上、化学物質によるiPSC多能性の誘導と増強、特定の分化細胞種の作製、iPSCの多能性およびゲノム安定性の維持。
これらのテーマは、臨床応用に向けたiPSCの作製と分化の効率を最大化する上で極めて重要である。細胞培養技術の進歩には、フィーダー細胞不要培養、動物由来成分不使用培地(ゼノフリー培地)、各種バイオマテリアルを利用した技術が含まれる。3次元(3D)細胞・バイオプリンティング技術は、PSCリソースおよび第二世代の直接的細胞再プログラム化(in vivo)と並び、特に有望な方向性を示している。
幹細胞研究および臨床の長期的目標は、神経変性疾患、脊髄損傷、心疾患、糖尿病など、細胞置換または組織再生が治療効果をもたらし得る多くの疾患に対する安全かつ有効な治療法の開発に焦点を当てている。
倫理的考察
幹細胞研究は、特に胚性幹細胞とクローニング技術に関して、重要な倫理的考察に対処し続けている。hESC研究のためのヒト胚の破壊は、多くの社会で論争の的となっており、国によって異なる規制が設けられている。
iPSCのような新興技術は、胚破壊を伴わない代替多能性細胞源を提供することで、一部の倫理的懸念に対処するのに役立っている。しかし、遺伝子操作、細胞提供に関する同意、および結果として得られる治療法への公平なアクセスに関して新たな倫理的疑問が生じている。
国際的な研究コミュニティは、様々な疾患に苦しむ患者への潜在的利益を最大化しつつ、幹細胞研究の倫理的進展を確保するための指針と規制の開発を続けている。
出典情報
原論文タイトル: Advances in Pluripotent Stem Cells: History, Mechanisms, Technologies, and Applications
著者: Gele Liu, Brian T. David, Matthew Trawczynski, Richard G. Fessler
掲載誌: Stem Cell Reviews and Reports (2020) 16:3–32
DOI: https://doi.org/10.1007/s12015-019-09935-x
この患者向け記事は、査読付き研究に基づき、複雑な科学情報を分かりやすく伝えることを目的とし、原論文の全ての本質的な知見とデータを保持しています。