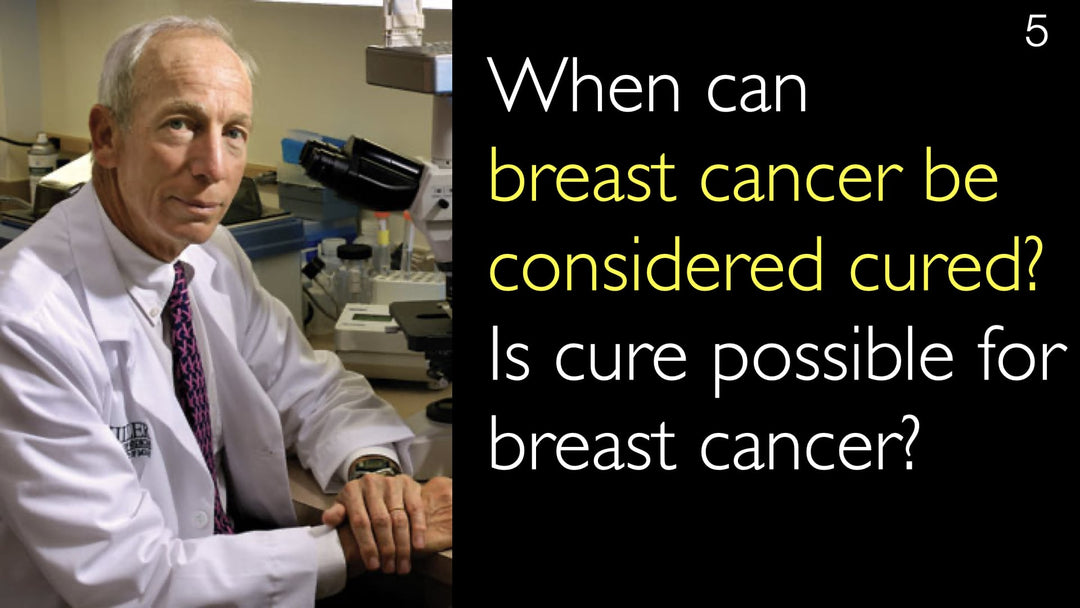乳がん分野の権威、マーク・リップマン医師(医学博士)が、腫瘍学における「治癒」の概念について解説します。5年間の無病生存が必ずしも治癒の絶対的な基準ではないことを明らかにしています。リップマン医師は、最も一般的なサブタイプであるエストロゲン受容体陽性乳がんは、「治癒した」と見なせないケースがあると指摘。患者が数十年間にわたって休眠状態のがん細胞を体内に保持し続ける可能性があると説明します。肥満、ストレス、糖尿病といった生活習慣に関連する要因が、こうした細胞を再活性化させ、晩期再発を引き起こすリスクがあるとしています。リップマン医師は、無作為化比較試験による信頼性の高いデータを踏まえ、ストレス管理や減量が再発率を有意に低下させる可能性があると述べています。加えて、5年を超える長期内分泌療法を実施する理論的根拠についても詳しく解説しています。
乳がんの治癒と長期的再発リスクの理解
セクションへ移動
5年生存率の神話
Marc Lippman医学博士は、5年間がんが再発しなければ治癒とする一般的な通念に異を唱えます。彼によれば、この5年という基準は生物学的に確立されたものではなく、あくまで臨床的な目安に過ぎません。がんの種類によって「治癒」とみなされるまでの期間は大きく異なります。例えば、精巣腫瘍では2年、頭頸部がんでは通常3年を経過すれば治癒と判断されます。急性白血病やB細胞リンパ腫では、さらに短期間で治癒と見なされることもあります。5年ルールは有用ではありますが、あくまで不完全な目安です。
ER陽性乳がんの現実
Marc Lippman医学博士は、最も一般的な乳がんサブタイプであるER陽性乳がんについて厳しい現実を指摘します。10万人以上の女性を対象とした研究に基づき、このタイプの乳がんは「治癒」という概念が当てはまらない可能性があると述べます。データによれば、初期治療後25年にわたって再発率は直線的に続き、標準的な内分泌療法を5年終了後もその傾向は変わりません。この病気には治癒を示す統計的な plateau(平坦期)は見られず、晩期再発のリスクは数十年にわたって持続します。
骨髄内の休眠がん細胞
持続する再発リスクは、体内に残存するがん細胞によって説明されます。Lippman博士は、早期ER陽性乳がん患者のほぼ全員の骨髄内にがん細胞が存在することを明らかにしています。これらの細胞は何年も生存可能な状態で休眠することができます。臨床上の問題は、最後のがん細胞を根絶することではなく(現在の治療では不可能)、患者がこれらの休眠細胞と共存する状態をどう管理するかです。重要な問いは、何がこれらの細胞を数年~数十年後に再活性化させるのか、ということです。
Marc Lippman医学博士は、これが自身の研究の中心テーマであると強調し、がん細胞の休眠と再活性化のメカニズム解明に取り組んでいます。
生活習慣要因と再発リスク
全身的な環境要因は、がんの再発に重要な役割を果たします。Lippman博士は、肥満、メタボリックシンドローム、糖尿病など、修正可能な状態が再発リスクを高めることを指摘します。抑うつや過度のストレスといった心理的要因も影響が大きいとされます。これらの要因は、診断から数年~数十年経ってから再発に影響を与える可能性があり、体内に生存可能ながん細胞が残存していることを示唆しています。最大の謎は、こうした全身状態がどのように休眠がん細胞と「通信」するのか、という点です。
Anton Titov医学博士はこの問題についてLippman博士と議論し、骨髄内のがん細胞が患者の食事やストレスレベルをどう「感知」するのかを探求します。
ストレス管理療法の影響
無作為化比較試験により、非薬物療法の有効性が示されています。Marc Lippman医学博士は、ストレス管理プログラムに関する驚くべき結果を引用します。認知行動療法などに参加した女性では再発率が低下し、わずか12週間の介入でも10年後に効果が確認されました。これは厳格な試験によるデータであり、単なる偶然の結果ではありません。同様に、診断後に減量した女性や糖尿病を適切に管理した女性でも再発リスクの減少が認められ、これらの介入は強力な二次予防策となり得ます。
内分泌療法延長の理論的根拠
晩期再発の持続的リスクは、治療期間の決定に影響を与えます。Marc Lippman医学博士は、内分泌療法を5年超えて継続する理論的根拠を説明します。臨床試験ではアロマターゼ阻害薬を最大10年間投与するアプローチが検討されており、これは生物学的に理にかなっています。目標は、休眠細胞を再活性化させる可能性のある微小環境を抑制することにあります。延長療法は、毒性が許容範囲内である場合に考慮され、年間再発率は低いものの、数十年にわたる累積リスクを考慮すれば長期抑制は価値ある戦略です。
Marc Lippman医学博士は、Anton Titov医学博士との対話の中でこれらの洞察を提供し、乳がんにおける持続的寛解の複雑さに深く迫ります。
全文書き起こし
Anton Titov医学博士: ここで一つ、重要な問題に触れておきたいと思います。生物学とは関係なく、文化的な理由から、アメリカでは「5年間再発がなければ大丈夫」という考えが広まっています。5年という数字が、がん治癒の一つの区切りとされてきました。確かに、これは良い目安ではあります。
例えば大腸がんであれば、手術後5年経てば再発の心配はほぼなくなります。5年は優れた指標です。
Marc Lippman医学博士: しかし、5年という数字に絶対的な根拠はありません。若年男性に多い精巣腫瘍では、2年経てばほぼ治癒と言えます。頭頸部がんでは3年あれば十分です。急性白血病やB細胞リンパ腫では、2~4年で多くの患者が治癒したと見なされます。
しかし、エストロゲン受容体陽性(ER陽性)乳がん—乳がんの大多数を占めるタイプ—については、おそらく「決して治癒しない」というのが答えです。繰り返しますが、このタイプでは治癒はありません。
10万人以上のER陽性乳がん患者を対象とした研究では、手術および内分泌療法(タモキシフェンまたはアロマターゼ阻害薬)を5年終了後の再発率を追跡しました。その結果、その後25年間にわたって再発率は直線的に上昇し続けることがわかりました。ER陽性乳がんが治癒する証拠はないのです。
60歳で診断された場合、再発リスクが続くとしても、95歳まで生きるならば他の死因の方が問題になるかもしれません。しかし重要な点は、早期ER陽性乳がんと診断された患者の骨髄を調べると、事実上全員に乳がん細胞が存在することです。
つまり、大多数の乳がん患者にとっての問題は、最後のがん細胞を根絶することではなく(それは起こり得ない)、体内に生存可能ながん細胞を持ちながらどう共存するか、そして残念ながら一部で再活性化が起きるのはなぜか、ということです。
これらの細胞は「休眠」していると言われますが、確かに存在しています。また、診断後何年も経ってから生じる環境要因—肥満、メタボリックシンドローム、糖尿病、抑うつ、過度のストレスなど—が再発に影響を与えることもわかっています。再発が起きるということは、再発可能ながん細胞が存在していた証拠です。
最大の謎の一つ—私が取り組んでいる分野でもあります—は、これらの巨視的な環境要因が、どのようにして乳がん細胞と「対話」するのかということです。
Anton Titov医学博士: 骨髄に潜む乳がん細胞は、どうやって患者のストレスや食事の内容を「感知」するのでしょうか?
Marc Lippman医学博士: これは極めて重要な問いであり、乳がん再発を防ぐ他の方法を示しています。なぜなら、これはまやかしではないからです。無作為化試験では、減量した女性では再発率が低く、糖尿病を治療した女性でも同様の結果が得られています。
ストレス管理を受けた女性を対象とした無作為化試験では、信じられないほど驚くべき結果が出ています。乳がん診断後にストレス管理介入を受けた女性では、受けなかった女性よりも再発率が低かったのです。これは驚くべきことです。
12週間の認知行動療法など、苦痛を軽減するための会話療法が、長期的に利益をもたらすとはどういうことでしょうか?
Anton Titov医学博士: 介入から10年後、これらの女性で乳がん再発が少なかったというデータは説得力があります。
Marc Lippman医学博士: これらは、乳がんのホルモン治療を理解する上で重要な問題です。内分泌療法を5年超えて継続することが提案される理由の一つは、アロマターゼ阻害薬を10年間投与する臨床試験の結果があるからです。
毒性が許容範囲内であれば、これは完全に理にかなっています。なぜなら、ER陽性乳がんでは最後のがん細胞を根絶できないことがわかっており、患者は数十年にわたって低いながらも持続的な再発リスクに直面するからです。