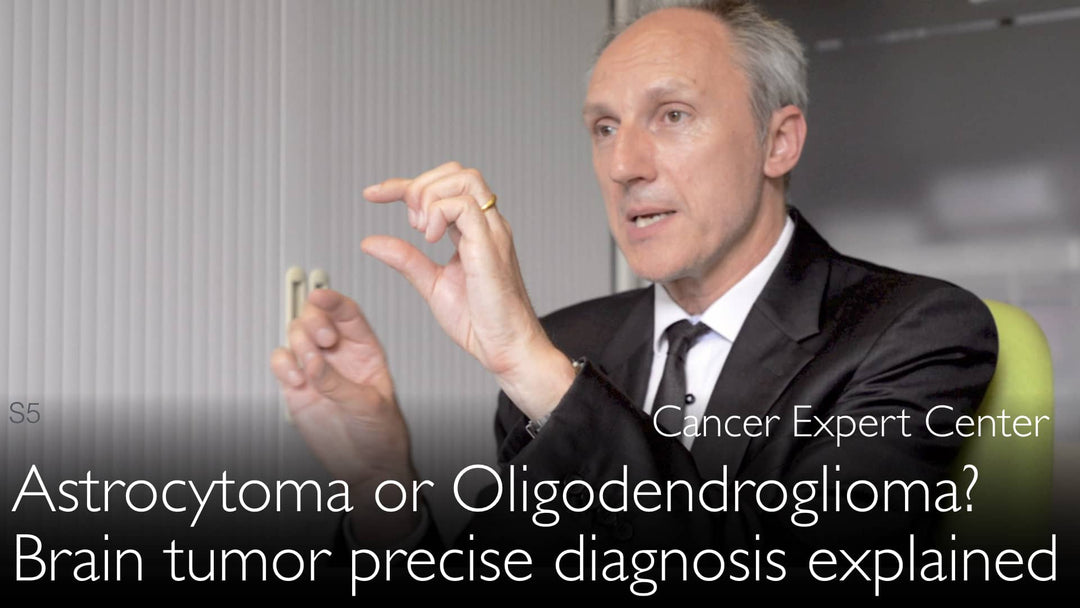1990年代の画期的な発見により、ケアンクロス博士は染色体1pおよび19qの同時欠失が乏突起膠腫の特徴的な所見であることを明らかにしました。医学博士セバスチャン・ブランドナー氏によれば、この共欠失は乏突起膠腫の約80%に認められる一方、他の脳腫瘍ではまれです。1p/19q共欠失の存在は、乏突起膠腫患者が化学療法や放射線療法に良好に反応することを示唆する予後因子となります。
乏突起膠腫と星細胞腫の分子検査:主要な遺伝子マーカー
セクションへ移動
分子検査導入前の神経膠腫分類の課題
分子診断が導入される前は、乏突起膠腫と星細胞腫の鑑別は顕微鏡検査のみに頼っており、診断に不確実性が生じることが少なくありませんでした。Sebastian Brandner医学博士によれば、従来の病理学的手法ではこれらの神経膠腫が似たように見えていたとのことです。遺伝子検査の導入により、客観的なバイオマーカーに基づく精密な腫瘍分類が可能となり、神経病理学は大きく変革されました。
1p/19q共欠失:乏突起膠腫のマーカー
1990年代、Cairncross博士による画期的な発見により、1番染色体短腕(1p)と19番染色体長腕(19q)の同時欠失が乏突起膠腫の特徴であると特定されました。Sebastian Brandner医学博士は、この共欠失が乏突起膠腫の約80%に認められる一方、他の脳腫瘍ではまれであると指摘しています。同博士が所属する英国の神経病理学部門では2003年に1p/19qの臨床検査を開始し、検査が治療計画の標準となるにつれて症例数が急速に増加しました。
IDH変異:神経膠腫の普遍的指標
Sebastian Brandner医学博士は、2008年のイソクエン酸脱水素酵素(IDH)変異の発見が新たな診断パラダイムを生み出した経緯を説明しています。Andreas von Deimling博士の研究により、1p/19q欠失を有する乏突起膠腫はすべてIDH変異も保有すること、一方で共欠失を伴わないIDH変異腫瘍は星細胞腫に分類されることが明らかになりました。この二重マーカーシステムは現在、世界保健機関(WHO)の神経膠腫分類基準の基盤となっています。
脳腫瘍診断法の進化
初期のPCR法から現代のシーケンシング技術に至るまで、分子検査法は著しく進歩しました。Brandner博士の研究室では、2003年に年間10症例の解析から始まり、現在では国家的な参照センターとして機能しています。現在のプロトコルでは染色体解析とIDH1/2変異検査を組み合わせ、神経膠腫患者の臨床判断を導く包括的な分子プロファイルを提供しています。
分子検査が治療方針に与える影響
1p/19q共欠失の存在は、乏突起膠腫患者における化学療法および放射線療法への良好な反応を予測する指標となります。Anton Titov医学博士は、分子検査の結果が治療プロトコルに直接影響を与えることを強調しています——共欠失腫瘍では通常、複合的な治療法が選択されます。IDH変異の有無も予後に影響し、IDH変異型神経膠腫は一般にIDH野生型腫瘍よりも進行が緩やかです。
先進的脳腫瘍検査の実施状況
Sebastian Brandner医学博士は、英国の神経病理学ネットワークが分子検査の広範な実施を推進している点を強調しています。同博士のセンターは1000~1200万人の人口をカバーし、複数の病院から検体を受け付けています。主要なセンターの大半では現在これらの検査を自施設で実施していますが、最適な患者ケアのため、施設間で一貫した結果を保証する標準化が継続的に進められています。
全文
Anton Titov医学博士: 脳腫瘍には多くの種類がありますが、乏突起膠腫は重要なカテゴリーの一つです。乏突起膠腫は比較的頻度の高い脳腫瘍形態であり、その先進的分子解析は治療計画の立案と患者のリスク層別化において極めて重要な役割を果たします。
Sebastian Brandner医学博士: この分野には研究と診断という二つの重要な側面があります。双方が不可欠ですが、私はまず診断に焦点を当てて説明します。
1990年代初頭、Cairncross博士は乏突起膠腫に特徴的な遺伝子マーカー——1番染色体短腕(1p)と19番染色体長腕(19q)という二つの染色体腕の共欠失——を発見しました。この画期的な知見は急速に広がり、最終的には臨床診断に組み込まれました。
過去10年から15年にわたり、治療決定が1p/19q共欠失の検出に依存するようになったため、分子診断の重要性はますます高まっています。
2008年、米国の研究コンソーシアムが乏突起膠腫および星細胞腫におけるイソクエン酸脱水素酵素(IDH)の変異を発見しました。1年後には、特定の軟部腫瘍および血液がんでIDH変異が同定されています。
その後間もなく、ハイデルベルグのAndreas von Deimling博士がIDH変異とこれらの神経膠腫の関連性について詳細な研究を行いました。同博士のチームは、1p/19q共欠失が乏突起膠腫では常にIDH変異と共存すること、一方で共欠失を伴わないIDH変異型脳腫瘍の別グループは星細胞腫に分類されることを確認しました。
Sebastian Brandner医学博士: 私の部門では2003年に1p/19q分子検査を確立し、当初は年間約10例の脳腫瘍を検査していました。2004年から2005年までに年間20~30検体まで規模を拡大し、PCR法を用いた診断法をさらに改良しました。
現在、私の研究室は英国全域の神経病理学部門にこの分子診断サービスを提供しています。
神経病理学会はこれらの診断検査を各施設で確立することを強く推奨しており、患者が遅滞なく正確な脳腫瘍診断を受けられるようにしています。英国の主要な神経病理学センターの大半は自施設で検査を実施していますが、私の部門は特に広い catchment area(受持区域)——1000万から1200万人をカバー——を担当し、多数の病院から脳腫瘍検体を受け入れています。
乏突起膠腫と星細胞腫は神経膠腫の二つの主要なタイプです。最適な治療戦略を決定するためには、精密な分類が極めて重要です。
場合によっては、これらの変異が陰性と予想される腫瘍に対しても、病理学的確認と腫瘍生物学の理解のために分子検査が実施されます。
Anton Titov医学博士: 分子バイオマーカーに関する理解が深まることで、より明確で精密な診断が可能となり、最終的には患者の転帰改善につながります。