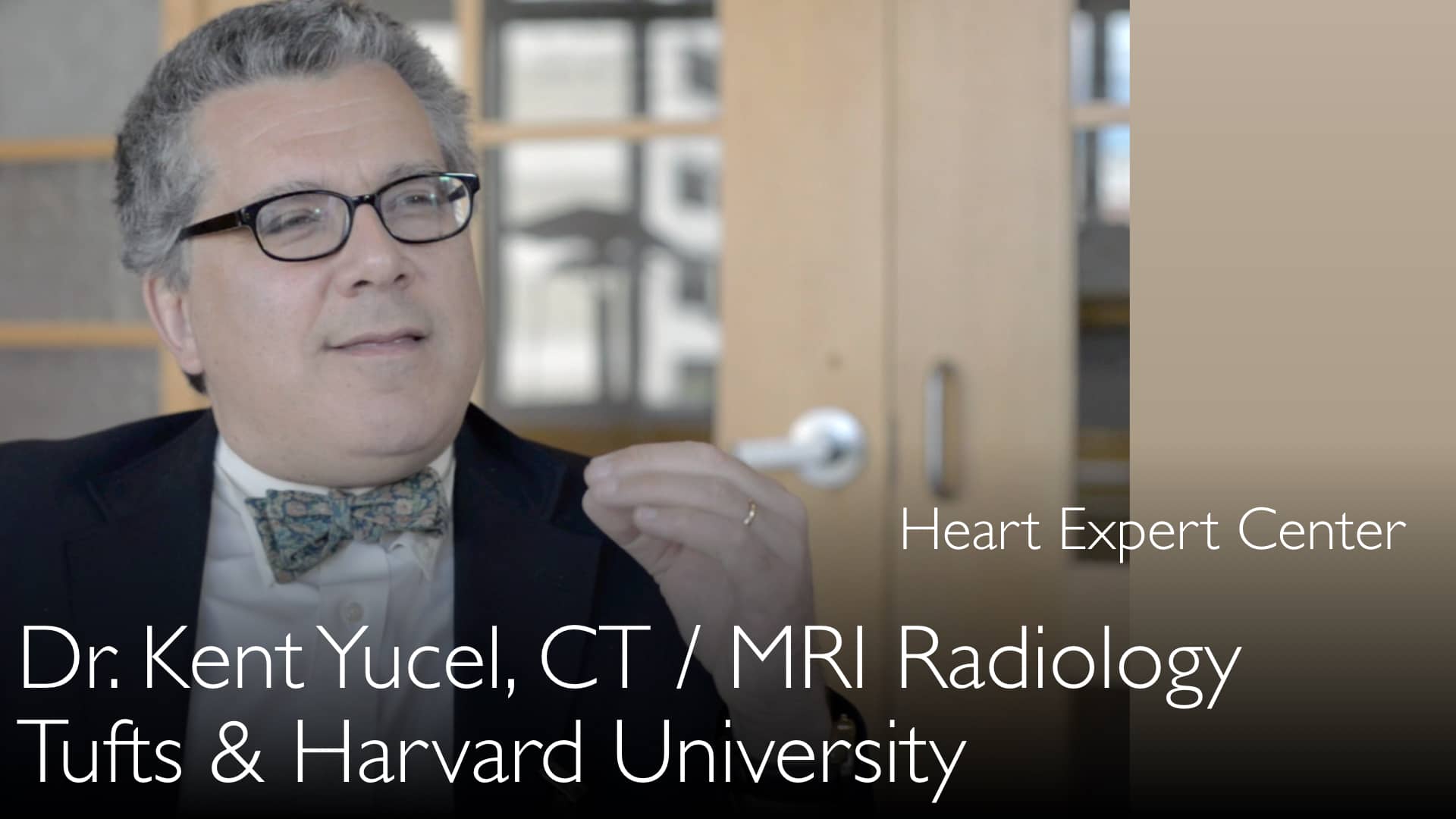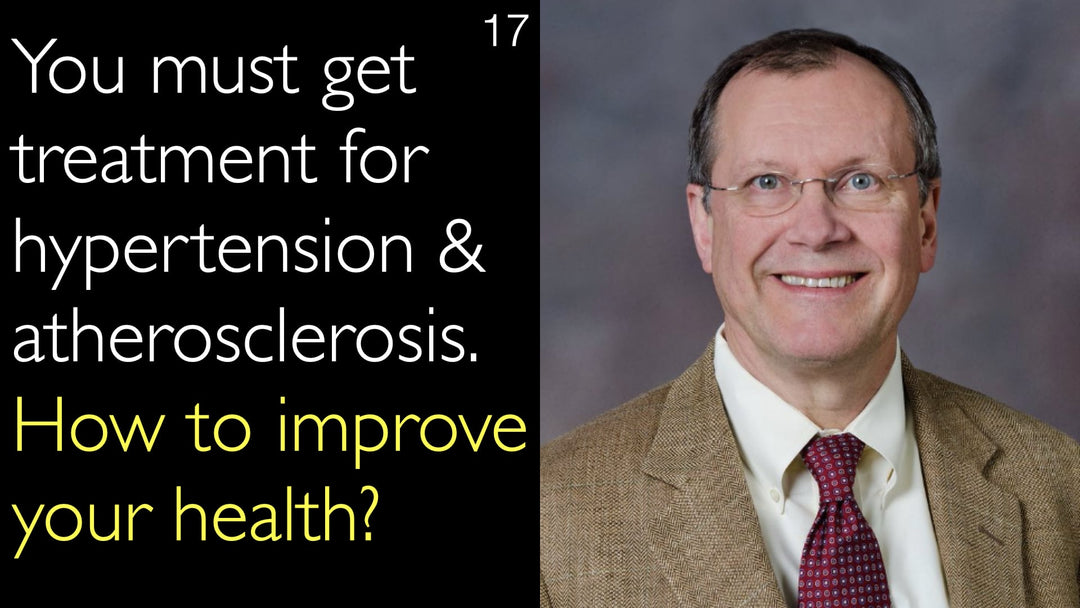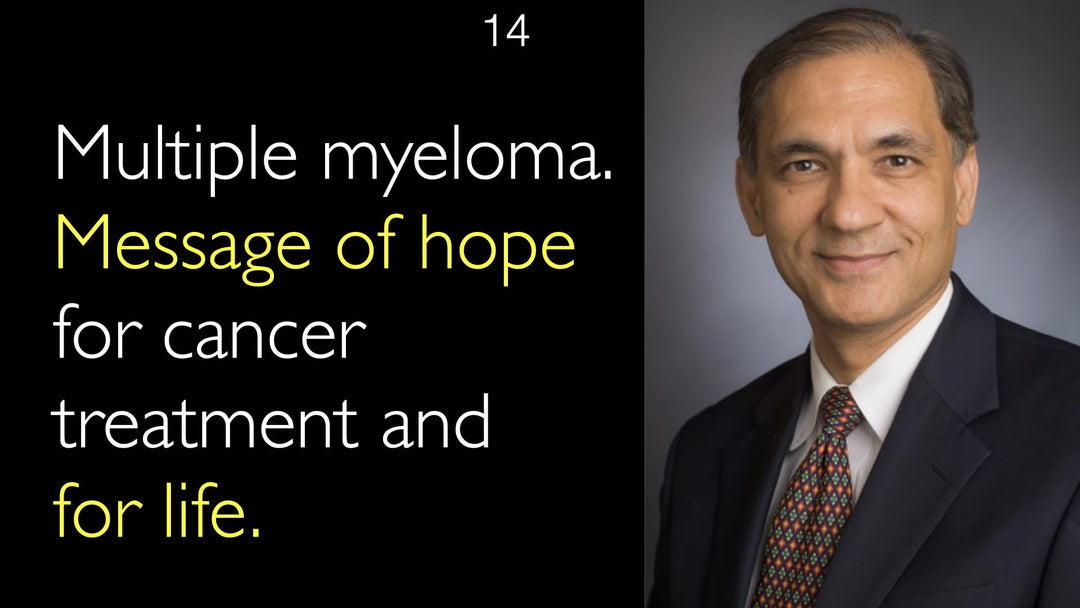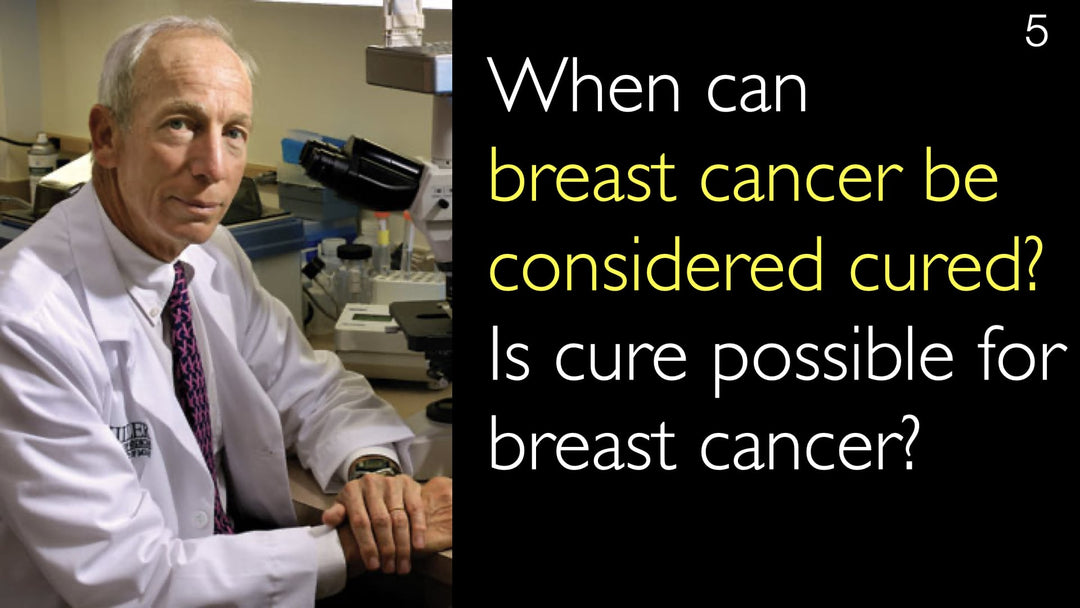放射線学および高度画像診断の権威であるKent Yucel医師(医学博士)が、全身CTおよびMRIがん検診で頻繁に認められる所見について解説します。多くの所見は小さな囊胞や古い瘢痕などの良性偶発所見であることを詳しく説明。Kent Yucel医師(医学博士)は、患者の不安や不要な追加検査に伴う重大なリスクを指摘。これらの検診法が診断的有用性に乏しく、死亡率改善効果に関するエビデンスが不足していることを強調しています。
全身CT・MRIがん検診で見つかる「偶発所見」とは
セクションへ移動
検診でよく見られる所見
全身CTやMRIによるがん検診では、しばしば偶発所見が認められます。放射線科医のKent Yucel医師によれば、こうした所見は主に2つに分類されます。最も多いのは、嚢胞(のうほう)と呼ばれる小さな液体のたまりです。これらは良性の構造物で、検診時にさまざまな臓器で見つかることがあります。
小さな嚢胞の診断が難しい理由
小さな嚢胞と潜在的な腫瘍を見分けることは、診断上の大きな課題です。Yucel医師は、適切なサイズの嚢胞であれば、放射線科医は確信を持って同定し、経過観察の必要はないと説明します。しかし検診では、画像特徴がはっきりしない微小病変が見つかることも少なくありません。この不確かさが確定診断を難しくし、臨床上問題のない所見が重大な懸念材料となってしまうのです。
良性の病変や斑点
嚢胞以外にも、検診スキャンでは他の良性の病変がしばしば見られます。Yucel医師によれば、これらは過去の感染症の痕跡、例えば肺炎による肺の瘢痕組織である可能性があります。肝臓の血管腫のような小さな良性腫瘍も、よくある偶発所見の一つです。嚢胞と同様、サイズが小さい場合には、長期的な経過観察なしに良性と断定することが難しい面があります。
患者の不安と経過観察のリスク
検査で異常が見つかると、患者は大きな不安を抱えることになります。Yucel医師は、過去には良性の斑点を理由に不必要な肺手術を受けた放射線科医の事例を挙げています。現在の標準的なプロトコルでは、経過観察として画像検査を繰り返すことが一般的です。患者によっては、病変に変化がないことを確認するため、6ヶ月または1年ごとに3~5年間、CTやMRIを継続して受ける必要が生じます。これにより、繰り返しの被曝や精神的な負担が生じてしまうのです。
検診の診断効率の低さ
全身検診にはリスクが伴い、利益を上回る場合が多いとされています。Yucel医師は、これらの検査が死亡率を改善するほど早期に重大ながんを見つけ出す証拠はほとんどないと指摘します。その過程で、多くの患者が良性所見の確認のために何年にもわたる不必要な経過観察を受けることになります。Anton Titov医師も、過剰治療を避け所見の意味を正しく理解するため、セカンドオピニオンを求める重要性をしばしば訴えています。
全文書き起こし
Anton Titov医師: がん検診目的のCTやMRI(磁気共鳴画像法)は広く行われています。検診のCTや全身MRIで典型的によく見られる所見にはどのようなものがありますか?これらの所見は、検診を受ける患者にとってどのような意味を持つのでしょうか?MRIやCTで小さな病変が見つかった場合、その後どうなるのでしょうか?第一線で活躍する放射線科医が、検診MRIおよびCTでよく見られる所見について議論します。
症状のない状態で行われるがん検診を目的としたMRIは、近年人気が高まっています。放射線科の専門家であるCT・MRIのエキスパートへのビデオインタビュー。MRIを用いた乳がん検診は現在、確立された方法です。全身MRIによるがん発見は、一般消費者向けに広く宣伝されています。
高危険群を対象とした肺がん検診のための低線量CTには有益性が認められる場合もあります。肺がん検診の利益とリスクについては新たなガイドラインが策定されています。一方、検診目的のCTやMRIの診断的有用性は限定的です。多くの場合、見つかるのは小さな嚢胞です。しかし医師も、それが嚢胞なのかがんなのか判断に困ることが少なくありません。その結果、被曝を伴う追加検査が繰り返し行われることになります。
CTやMRIで見つかった所見の意味を正しく理解し、過剰な検査や治療を避けるためには、セカンドオピニオンを求めることが重要です。セカンドオピニオンは、最適な治療戦略を選択する上で有用です。がん診療においては、セカンドオピニオンを得て治療方針に自信を持ちましょう。
Anton Titov医師: がん検診のCTやMRIで見つかる所見の99%は、臨床的に意義の乏しい偶発所見であるとおっしゃいました。それでも、検査で何らかの所見が指摘されると、患者は大きな不安を感じます。そしてこうした偶発所見は、しばしば侵襲的な方法で経過観察されることになります。現在、脳や胸部、腹部、骨盤など、全身のMRIやCTを用いたがん検診が行われています。検診MRIでよく見られる所見には、どのようなものがありますか?
Kent Yucel医師: CTやMRIの偶発所見は、大きく2つに分類できます。一つは小さな液体のたまりで、私たちは嚢胞と呼んでいます。これらはさまざまな臓器に発生します。嚢胞は通常、良性です。問題は、嚢胞が小さい場合、それが確実に嚢胞であると判断することが非常に難しい点です。
通常、私たちは別の理由で検査を受けた患者さんでこうした嚢胞を認めます。適切なサイズであれば、それを嚢胞と判断し、経過観察の必要はありません。しかし検診としてMRIやCTを行う場合、問題が生じることがあります。こうした小さな嚢胞が見つかると、それが本当に嚢胞なのか確信が持てないのです。そこに課題があります。
もう一つのパターンとして、良性の斑点と呼ばれる所見があります。肺では、過去の肺炎や感染症の痕跡である可能性があります。肝臓に生じることもあります。これらは小さな良性腫瘍のこともあります。やはりサイズが小さい場合、臨床的に重要かどうかの判断が難しくなることがあります。
検診CTが導入された当初、アメリカである有名な放射線科医がいました。彼は検診CTを受け、肺に斑点があると指摘されました。その後、肺切除術を受けることになったのです。結局、その斑点は何の問題もないものだったことが判明しました。
この経験から、私たちはCTで見つかる斑点や病変に対して過剰な対応をしないよう学びました。現在では、検診のCTやMRIで何らかの所見が認められた場合、経過観察として画像検査を繰り返すことが標準的です。そのため、多くの患者が6ヶ月または1年ごとに再来し、3年、4年、場合によっては5年間もCTやMRIを受け続けることになります。病変に変化がないことを確認するためです。
これが検診MRIのリスクです。検診手法全体に伴う大きなリスクと言えます。多くの患者が、取るに足らない所見であることを証明するために、3年から5年間も追加の画像検査を受け続けるという結果を招くからです。
その一方で、検診のCTやMRIによって重大な病変を早期に発見し、死亡率を改善するという明確な証拠はほとんどありません。がん検診のCTやMRIでよく見られる所見について、放射線科の第一人者であるCT・MRIの専門家へのビデオインタビューでした。偶発所見に対してどのように対応すべきでしょうか?