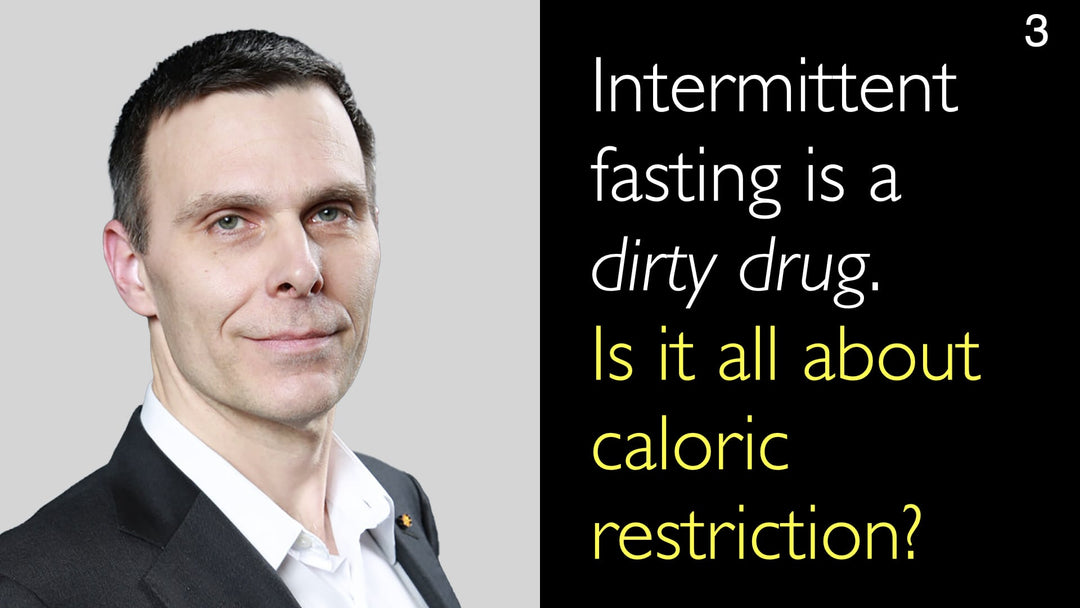老化と長寿研究の世界的権威であるMatt Kaeberlein医学博士が、カロリー制限と間欠的断食が健康寿命(ヘルススパン)に与える影響について解説します。博士は、こうした食事介入が生物学的老化に及ぼす可能性のあるメリットについて考察。さらに、一般的なダイエット文化で見過ごされがちな重大なリスクや副作用についても言及します。食事の変更は、生体に広範な影響を与える複雑な介入であることを指摘し、動物実験と臨床応用の間にあるギャップについても探求します。
カロリー制限と間欠的断食:効果、リスク、そして生物学的影響
セクションへ移動
カロリー制限と肥満予防
マット・ケーベルライン医学博士は、カロリー制限と老化に関する根本的な疑問に答えています。彼は、その効果が単なる肥満予防を超える可能性が高いと説明します。実験用齧歯類の研究では、健康的な体重の動物と比べても、カロリー制限をした動物に寿命延長効果が確認されています。ケーベルライン博士は個人的見解として、カロリー制限はおそらくヒトの生物学的老化に良い影響を与えると述べていますが、ヒトの寿命が長いため、研究は極めて困難だと警告しています。
ヒトへの応用と潜在リスク
ケーベルライン博士は、長寿戦略においてリスクと報酬のバランスを考慮することの重要性を強調します。ヒトは実験動物と異なり、遺伝的に多様で複雑な環境で生活していると指摘。長期的なカロリー制限には、インフルエンザやCOVID-19などの感染症への感受性が高まるといった重大なリスクが伴います。博士は、食事法の提唱者がこうした悪影響や副作用を評価していないことが多いと警告し、栄養戦略にも副作用があるという事実が文化的に見落とされていると強調します。
症例研究:ロイ・ウォルフォード
アントン・チトフ医学博士は、著名なカロリー制限研究者で『120歳の食事法』の著者であるロイ・ウォルフォードを例に挙げますが、彼は79歳で亡くなりました。ケーベルライン博士は、ウォルフォードがALS(筋萎縮性側索硬化症)を患っていたことを確認していますが、食事法との関連は推測の域を出ません。この症例は、極端な食事介入を実践する少数の個人からのデータを解釈する難しさを示しています。特に、長期的なカロリー制限の実践者が110歳に達した例すら、現時点で確認されていません。
間欠的断食とカロリー摂取
チトフ博士は、間欠的断食や断食模倣食が単にカロリー制限の言い換えではないかと問います。ケーベルライン博士は、動物研究では間欠的断食の効果の大部分が実際には付随するカロリー制限によるものだと説明。等カロリー条件(総摂取カロリーが同じ場合)では、時間制限食による寿命への利益は、真のカロリー制限に比べて小さいかもしれません。ヒトにおいては、これらの戦略は主に正常体重の維持に価値があり、追加の抗老化効果をもたらすものではないと博士は考えています。
「不純な薬物」としての食事介入
ケーベルライン博士は、食事介入を「不純な薬物」とする重要な概念を紹介します。薬理的介入には副作用が認識される一方、食事変更の副作用はめったに考慮されないと指摘。飢餓、栄養失調、感染症への感受性亢進は、カロリー制限の実際の副作用です。博士は、いかなる食事介入も生物学的には最も非特異的な医薬品よりもはるかに「不純」であり、数百のタンパク質に影響し、膨大な生物学的変化を引き起こすと強調。この視点は、栄養介入の複雑な現実を理解する助けになります。
全文書き起こし
アントン・チトフ医学博士: 最近執筆された食事と老化に関する科学記事で、共著者とともにいくつか興味深い点を指摘されていますね。その一つは、カロリー制限の効果が単に肥満回避の助けになるだけなのか、つまり「魔法」はないかもしれない、ということです。これについてどうお考えですか?
マット・ケーベルライン医学博士: 合理的な質問だと思います。私の個人的見解では、その可能性は低いです。肥満は、実験用齧歯類でもヒトでも、老化に伴う様々な健康悪化と関連し、ほぼ確実に原因となります。正常体重の維持は確かに有益です。マウスでは、中程度の脂肪量を持つ健康的体重と比べても、カロリー制限からさらなる寿命延長効果が得られます。
ですから、カロリー制限の効果が単なる肥満予防によるものとは考えにくい。ヒトでは答えがより難しくなります。老化が遅く寿命も長いため、長期的なカロリー制限の対照研究は事実上不可能です。その文脈では、中程度または重度の長期的カロリー制限がヒトの老化生物学に良い影響を与えるかどうか、確信は持てません。
推測の域ですが、カロリー制限が肥満予防を超えてヒトの生物学的老化に良い影響を与えるだろうと私は考えています。懸念は、ヒトが複雑な環境に住み遺伝的多様性があるため、実験動物に基づく研究では、中~重度の長期的カロリー制限に伴うリスクが過小評価されがちな点です。
健康的長寿を最大化する戦略では、常にリスクと報酬の比率を考える必要があります。生物学的老化を遅らせ寿命を延ばす報酬は大きいですが、どんな戦略にもリスクが伴います。
カロリー制限の場合、明らかなリスクの一つは、慢性的な制限により感染症リスクが高まる、または感染後の戦闘能力が低下する可能性です。推測ですが合理的だと思います。仮にそうなら、老化が遅くても、インフルエンザやCOVID-19に感染し、栄養制限状態のために戦えず死亡しては意味がありません。
質問に明確に答えにくい点を強調するためです。たとえカロリー制限が老化面で大きな利益をもたらすとしても、ヒトにおける長期的リスクが利益を上回ると確信していません。これが私たちが指摘したかった点の一つです。インターネット上で食事法を宣伝する人々の一部は、潜在的な悪影響や副作用を真剣に評価していません。
文化的に、私たちは食事法や栄養戦略に副作用があると考えないよう訓練されていますが、現実には存在します。これを理解することが重要です。
アントン・チトフ医学博士: レビューでは、著名なカロリー制限研究者ロイ・ウォルフォードにも言及されていますね。彼は自身の提唱する120歳には程遠い79歳で亡くなりました。死因をご存知ですか?
マット・ケーベルライン医学博士: 私の理解では、ウォルフォード医師は一種のALS(筋萎縮性側索硬化症)を患っていたようです。それが公的なカロリー制限の実践と関連するかは完全な推測で、誰にもわかりません。これはカロリー制限実践者からの症例報告データを解釈する際の課題です。対象が常にごく少数だからです。
しかし要点は妥当です。彼は『120歳の食事法』を書き、カロリー制限が多くの人を120歳に導くと主張しましたが、自身は到達できませんでした。私の知る限り、長期的カロリー制限の実践者が110歳に達した例すらありません。
これはカロリー制限が極めて健康的な老齢を可能にするという考えを反証するものではありませんが、現時点でそれを支持する十分なデータはないと思います。
アントン・チトフ医学博士: おそらくそれが、間欠的断食や断食模倣食に関心が集まる理由なのでしょう。しかし再び、疑問は総カロリー量の対照がない点です。実際、これらは単にカロリー制限の言い換えである可能性があります。これらの食事修正について何がわかっていますか?
マット・ケーベルライン医学博士: 実験動物とヒトとで分けて考えることが重要です。動物研究では、この疑問に答える研究がいくつかあります。隔日断食のような間欠的断食で、寿命や健康寿命の指標が有意に増加したとする報告があります。
しかし、そうした研究を詳しく見ると、寿命に有意な効果があったほぼ全ての場合、マウスはカロリー制限もされていました。給餌日でも不足分を補っていなかったのです。ですから、効果がカロリー制限によるものか、時間制限給餌そのものによるものか、分離は困難です。
これはやや不明確な領域です。現在、異なる時間制限給餌法を用いた研究が進んでいます。現時点での私の見解は、等カロリー条件では間欠的断食から小さな寿命利益が得られる可能性はあるものの、真のカロリー制限による効果規模には遠く及ばない、ということです。
実験動物で観察される利益の大部分はカロリー制限に由来します。等カロリーの時間制限給餌から小さな利益が得られるかもしれません。ヒトでは、時間制限給餌や間欠的断食の注意深く対照をとった中期的研究さえ行われていないため、単にわからないのです。
私の個人的見解は、時間制限給餌や間欠的断食が正常体重維持や肥満防止に役立つのであれば、それ自体非常に価値があるということです。これらの戦略が、単に肥満でないこと以上の大きな利益をもたらすと信じる十分な理由は現時点ではありません。ただし、私は間違っているかもしれません。これが、現時点のヒトデータと利用可能な動物研究に基づく私の見解です。
アントン・チトフ医学博士: これは非常に興味深いデータです。一般の人々は明らかに、食事療法やカロリー制限を長寿の万能薬と同一視しがちです。あなたは正当にも、免疫系やその他の非制御条件など、現実世界のリスクを強調されています。マウスでは条件が非常によく制御されていますが。
マット・ケーベルライン医学博士: これは私が積極的に発言を続けている分野です。研究者も一般の方々も、食事摂取量を大きく変えると、それに伴う生物学的影響が多数生じることを十分認識していないと考えます。生物学の基礎知識があれば、これは当然の真実です。
カロリー制限や隔日断食を行うと、生物学的影響が生じます。通常見過ごされがちな点は、こうした介入には副作用が伴うことで、医薬品の副作用と非常に似ていることです。処方薬については、標的効果に加えて副作用リスクがあるという考えに慣れています。
しかし人々は食事療法に関してはそのように考えません。この点を強調することが重要です。カロリー制限の副作用には重篤なものがあり、例えば感染症への感受性亢進は死亡リスクにつながり得ます。栄養失調も潜在的な副作用です。しかしもっと一般的で理解しやすい副作用もあります。
空腹感は副作用です。これはカロリー制限の目的とする効果ではありませんが、大多数の人にとって現実的かつ不快な症状です。もし空腹感や腹痛を引き起こす薬を服用したなら、それは副作用と見なされるでしょう。人々は食事介入についてそのように考えないのです。
これが良いとも悪いとも言っているのではありません。単に認識することが重要だということです。同等に重要なもう一つの認識は、低分子医薬品が特異的生化学的効果を持てるのに対し、食事介入は「最も不純な医薬品」よりもはるかに「不純」だということです。つまり、栄養摂取を劇的に変化させた時の下流の生物学的変化は膨大である、という意味です。
おそらく数百種類のタンパク質が、遺伝子発現レベルまたは生化学レベルで変化します。カロリー制限、間欠的断食、時間制限食は、オフターゲット効果の観点では最も不純な医薬品に属します。繰り返しますが、これが良いとも悪いとも言いません。これは大多数の人々が考えもしない生物学的現実なのです。
アントン・チトフ医学博士: これは非常に重要な知見です。私がロックフェラー大学で博士号を取得中、酵母を研究していた時、栄養価の低い培地で一晩培養し発現パターンの変化を調べる初期の遺伝子チップ実験を行いました。その際、数千の遺伝子にわたる極めて顕著な影響を確認しました。酵母培地のごく軽度の一晩のカロリー制限だけで、パターンが完全に変わり、影響は非常に深刻でした。まさに先生がおっしゃった通り、「最も不純な効果」なのです。クリーンな低分子医薬品とは対照的です。