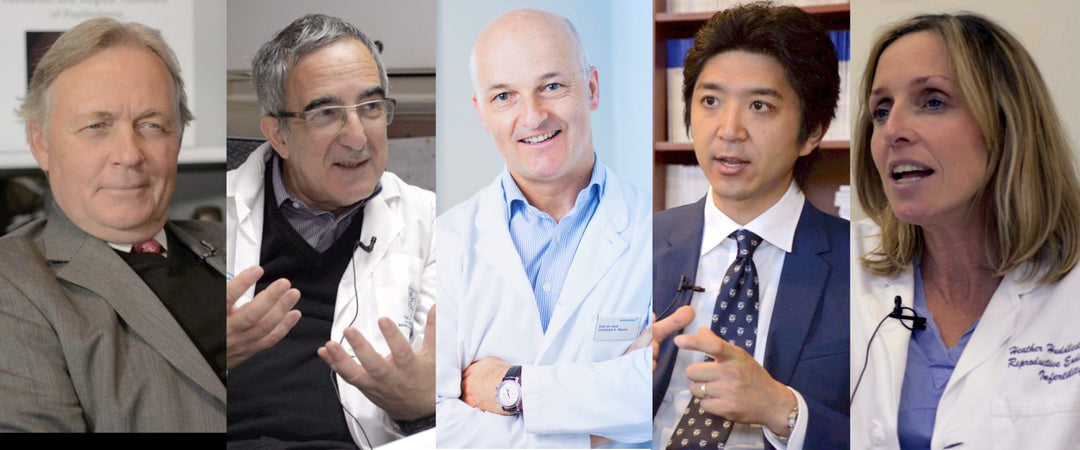本総説では、免疫系が感染症への防御と自己組織への攻撃回避のバランスをいかに維持するか、すなわち「免疫寛容」のメカニズムについて解説する。この均衡に関する近年の画期的知見は、短期治療で長期効果が期待できる自己免疫疾患・アレルギー・移植医療の新たな治療法開発につながっている。また、チェックポイント阻害薬ががん治療に有効である一方で自己免疫性の副作用を生じうる機序を詳述し、免疫恒常性を支える微妙な均衡の重要性を浮き彫りにする。
免疫寛容の理解:自己免疫疾患と臓器移植への新たな希望
目次
- はじめに:免疫バランスの課題
- 免疫寛容を維持する体の仕組み
- 胸腺:体内の免疫教育センター
- 末梢寛容:バックアップセキュリティシステム
- 制御性T細胞:体内の平和維持部隊
- 新たな寛容誘導療法
- 臨床応用と意義
- 研究の限界と課題
- 患者への推奨事項
- 情報源
はじめに:免疫バランスの課題
長年にわたり、科学者たちは免疫系がどのようにして異物と自己組織とを見分けているのかを解明しようとしてきました。この仕組みは「免疫寛容」と呼ばれます。このシステムがうまく働かなくなると、食物アレルギーや自己免疫疾患(体が自分自身を攻撃する状態)、臓器移植の拒絶反応など、重篤な症状を引き起こす可能性があります。
免疫寛容に関する研究は1950年代から始まりましたが、免疫系の理解が進んでも、有効な治療法の開発は困難でした。しかし近年、画期的な進展があり、臓器移植やアレルギー疾患、自己免疫疾患に対する新しい治療法が成果を上げています。
新しいペプチド製剤や特定の免疫細胞を標的とする抗体、細胞療法などは、短期間の治療で長期的な効果をもたらす可能性があります。これにより、継続的な投薬が必要なくなるかもしれません。これは、重い副作用を伴う生涯にわたる免疫抑制を必要とする従来の治療法からの大きな転換点です。
免疫寛容を維持する体の仕組み
免疫系は、寛容を維持するために複数の高度な仕組みを備えています。「免疫無応答性」とは、有害となりうる免疫細胞が不活性化されたり、排除されたり、あるいは制御細胞に変換されるなど、いくつかの保護状態を指します。
現在開発が進む寛容誘導薬は、アレルギー疾患や自己免疫疾患の治療と予防を目指しています。同時に、生涯にわたる免疫抑制なしで臓器や組織の移植を可能にします。近年成功を収めている治療法の一部は、実際には免疫寛容を破ってがんを治療するものですが、これらは時に自己免疫疾患を引き起こすこともあります。
がん治療のために免疫寛容を破ることと、免疫の恒常性を保つこととの微妙なバランスは、免疫調節の複雑さを物語っています。本稿では、新しい治療法の有望な標的であるT細胞と、その免疫反応の促進と抑制という二面性に特に焦点を当てます。
胸腺:体内の免疫教育センター
胸腺は、免疫反応を調整する重要な白血球であるT細胞が生まれ、訓練される場です。1960年代初頭、研究者たちは適応免疫系の基盤を成す2種類の免疫細胞、T細胞とB細胞を特定しました。
T細胞はいくつかの重要な役割を担います:B細胞が抗体を作るのを助け、感染した組織や異物を直接攻撃し、免疫反応を調節します。それぞれのT細胞は特定の標的を認識する独自の受容体を持っており、この多様性によって免疫系は無数の脅威に対処できるのです。
T細胞が成熟する過程では、胸腺内で2つの重要な選択が行われます。まず陽性選択では、T細胞が自身のMHC分子(主要組織適合遺伝子複合体分子:免疫細胞がタンパク質の断片を提示する役割を持つ)を通じて異物を認識できるかどうかが確認されます。
次に陰性選択では、自己組織に過剰に反応するT細胞が排除されます。髄質胸腺上皮細胞(mTECs)と呼ばれる特殊な細胞は、AIRE(自己免疫調節因子)というタンパク質を発現し、発達中のT細胞に数千種類もの組織特異的タンパク質を提示することで、自己反応性細胞を効果的に除去します。
この過程の重要性は、AIRE遺伝子に変異がある人に発症する重篤な多臓器自己免疫疾患、自己免疫性多腺性内分泌症候群1型(APS1)によって示されています。胸腺での教育が自己免疫疾患の予防に中心的な役割を果たしている証拠です。
末梢寛容:バックアップセキュリティシステム
胸腺が効率的に働いていても、一部の自己反応性T細胞は末梢に逃れ出るため、追加の安全機構が必要となります。末梢寛容は、胸腺以外の場所で免疫反応を制御する複数の細胞とプロセスを含みます。
T細胞の活性化には2つのシグナルが必要です:1つはT細胞受容体が標的を認識すること、もう1つはCD28などの共刺激分子が抗原提示細胞上のCD80/CD86と結合することです。これらの共刺激経路を遮断すると、自己免疫疾患や移植の動物モデルで示されているように、抗原特異的な寛容を誘導できます。
同じく重要なのが、免疫活性化を抑制するチェックポイント経路です。CTLA-4やPD-1(プログラム細胞死1)などの分子は、免疫系のブレーキとして働きます。これらのチェックポイントが阻害されると(がん免疫療法など)、自己免疫が悪化することがあり、これらが寛容維持に果たす役割の大きさを示しています。
チェックポイント阻害剤は、悪性黒色腫や非小細胞肺がんなどの治療に革命をもたらしましたが、自己免疫性の副作用を引き起こすこともあり、効果的な免疫反応と有害な自己免疫とのバランスの難しさを浮き彫りにしています。
制御性T細胞:体内の平和維持部隊
制御性T細胞(Tregs)は、免疫バランスの維持に不可欠な特殊化された細胞です。これらの細胞は、FOXP3(フォークヘッドボックスP3)という主要な制御タンパク質を発現する自己反応性T細胞から分化します。FOXP3は、攻撃ではなく抑制するようにプログラムするスイッチのような役割を果たします。
Tregsには主に2種類あります:陰性選択の過程で胸腺で生まれる胸腺由来Tregs(tTregs)と、抑制因子に曝露された通常のT細胞から組織内で分化する末梢由来Tregs(pTregs)です。これらの細胞は、他の制御細胞と協力して、自己免疫反応から体を守ります。
FOXP3の機能が損なわれると(IPEX症候群のような遺伝子変異や薬物的干渉により)、骨髄移植をしなければ幼少期に命を落とすこともある重篤な自己免疫疾患が引き起こされます。これは、免疫恒常性の維持においてTregsが極めて重要であることを示しています。
Tregsは複数の抑制メカニズムを使います:共刺激を阻害する高レベルのCTLA-4を発現し、インターロイキン-10やTGF-β(形質転換増殖因子ベータ)などの抗炎症性サイトカインを産生し、ATPをアデノシンに変換して免疫反応を抑制します。また、腸内細菌叢にも影響を与え、短鎖脂肪酸などの微生物産物はTregsの機能を高めることができます。
新たな寛容誘導療法
従来、自己免疫疾患と移植拒絶反応は、重い副作用を伴う広範な免疫抑制剤で治療されてきました。新しいアプローチでは、持続的な治療なしで、より標的を絞った形で寛容を誘導することを目指しています。
造血幹細胞移植(HSCT)は、自己反応性細胞を除去し、回復過程で新しい免疫細胞が寛容を獲得することで、免疫系を「再起動」させることができます。自家HSCTは多発性硬化症の進行を止める可能性を示しており、自家およびドナー由来のHSCTを組み合わせることで、免疫機能を保ちながらドナー組織への持続的な寛容を生み出せます。
アレムツズマブ(抗CD52抗体)、リツキシマブ、オクレリズマブ、オビヌツズマブ(いずれもB細胞を標的とする)などの抗体を用いた免疫細胞除去療法は、一部の自己免疫疾患で病状の進行を遅らせることに成功しています。これらの治療は、自己抗原をT細胞に提示する自己反応性B細胞を除去することで効果を発揮します。
その他のアプローチとしては、モノクローナル抗体や可溶性チェックポイント受容体を用いた共刺激遮断、自己免疫疾患のためのチェックポイント作動薬、増殖させた制御性T細胞の治療的投与などがあります。
臨床応用と意義
免疫寛容の仕組みに関する新たな知見は、自己免疫疾患やアレルギーを持つ患者、そして臓器移植を必要とする患者にとって重要な意味を持ちます。生涯にわたる免疫抑制に伴うリスクに代わり、短期間の寛容誘導治療が長期的な効果をもたらす可能性があります。
がん患者にとって、チェックポイント阻害剤は治療成績を大きく変えましたが、自己免疫性の副作用も伴い、注意深い管理が必要です。腫瘍を攻撃するために免疫寛容を破ることと、免疫の恒常性を保つこととのバランスを理解することは、これらの治療法を最適化する上で極めて重要です。
免疫系と腸内細菌叢との関係は、新たな治療の可能性を開きます。短鎖脂肪酸などの微生物産物は制御性T細胞の機能を高めるため、免疫疾患の治療を補完する食事介入の可能性が示唆されています。
免疫寛容の仕組みは加齢とともに変化するため、治療アプローチは小児と成人で異なるかもしれません。胸腺は成人期に退縮するため、末梢での寛容経路がより重要になります。
研究の限界と課題
大きな進展があった一方で、寛容研究を臨床現場に応用する上ではいくつかの課題が残されています。動物モデルで成功した多くのアプローチが、ヒトでの試験では同じほどの効果を示していません。
免疫反応や遺伝的背景には個人差があるため、寛容誘導戦略も個別化される必要があるかもしれません。免疫調節には多数の冗長な経路が関わるため、单一の成分を標的とするのは困難です。
新しい寛容誘導アプローチに関する長期的な安全性データは、特に長期にわたる免疫調整に伴う発がんリスクの面で、まだ限られています。効果的な免疫と寛容との微妙なバランスを保つためには、過剰な免疫抑制や自己免疫を避けるよう、治療を注意深く調整しなければなりません。
さらに、現在のほとんどのアプローチでは、何らかの形での初期免疫抑制やコンディショニングが必要であり、それ自体がリスクや副作用を伴います。侵襲の少ない寛容誘導法の開発は重要な目標です。
患者への推奨事項
自己免疫疾患、アレルギー、臓器移植に直面する患者にとって、免疫寛容の理解が進んだことは、副作用が少なくより標的を絞った効果的な治療法への希望となります。患者が知っておくべきポイントは以下の通りです:
- 新しい治療選択肢について医療提供者と相談する―従来の広域免疫抑制薬だけでなく、新しい寛容誘導療法が適応となる可能性も探りましょう。
- 免疫の活性化と抑制のバランスを理解する―がんに対する免疫力を高める治療は自己免疫リスクを上げる可能性があり、自己免疫を抑制する治療はがんの監視機構に影響を与える可能性があります。
- 腸と免疫の関係を考慮する―食事や腸内細菌叢の状態が免疫寛容に影響する可能性が研究で示されているため、栄養面でのアプローチについて医療チームと話し合いましょう。
- 適切な場合は臨床試験に参加する―多くの新しい寛容誘導アプローチはまだ開発段階にあり、進展のためには患者のボランティアが必要です。
- 免疫調整治療では副作用を注意深く観察する―新たな症状が出た場合は、速やかに医療提供者に報告してください。
これらの進歩は有望ですが、患者は疾患の重症度、治療歴、全身の健康状態などを考慮し、自身の状況に最適なアプローチを医療チームと緊密に話し合って決める必要があります。
出典情報
原題: Tolerance in the Age of Immunotherapy
著者: Jeffrey A. Bluestone, Ph.D., and Mark Anderson, M.D., Ph.D.
掲載誌: The New England Journal of Medicine, 2020年9月17日
DOI: 10.1056/NEJMra1911109
この患者向け記事は査読付き研究に基づき、原論文の科学的な内容をすべて保持しつつ、教育を受けた患者が複雑な免疫学的概念を理解できるようにすることを目的としています。