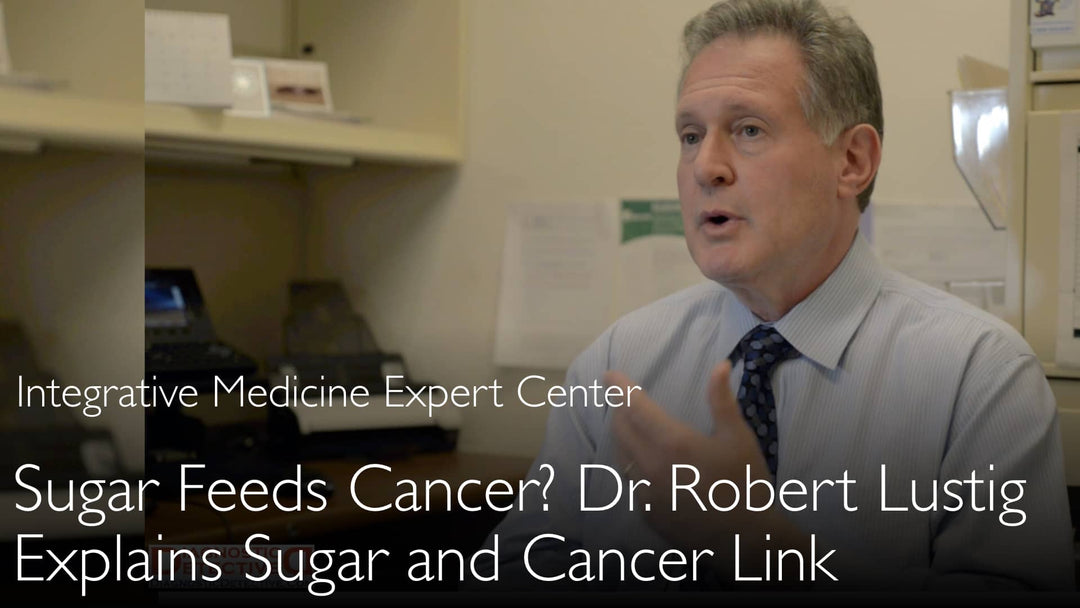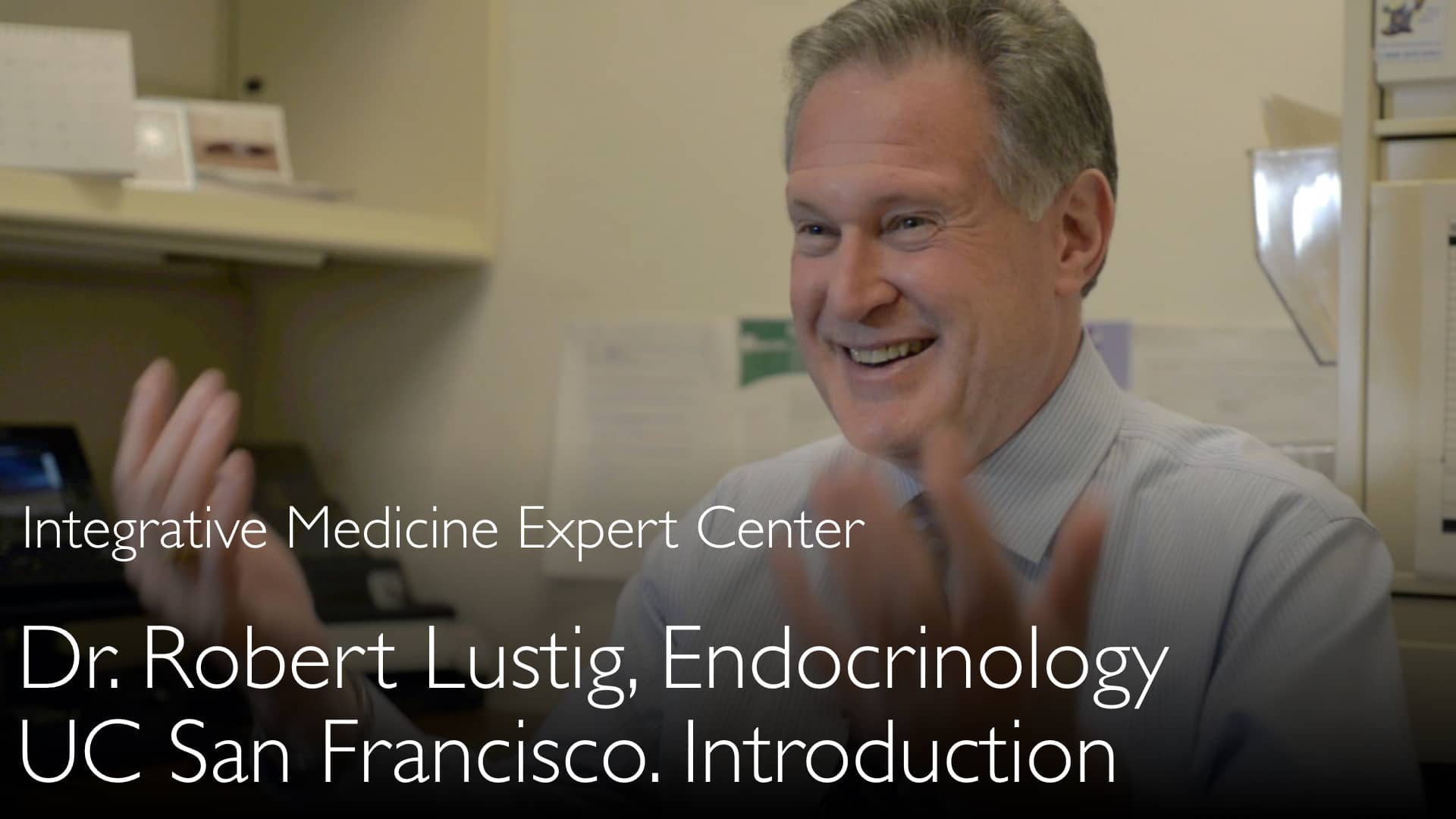小児内分泌学・栄養学の権威であるロバート・ラスティグ医学博士が、過剰な糖分摂取とがんリスク上昇との間に見られる強力な関連性について解説します。博士は、ワールブルク効果を通じてがん細胞の増殖を促すインスリンおよびインスリン様成長因子(IGF)の役割を詳しく説明。直接的な因果関係はまだ確定していないものの、ラスティグ博士は、西洋式の食生活の影響を受ける前の北極圏イヌイット集団で観察された低いがん発生率など、機序的・疫学的・歴史的証拠に裏打ちされた有力な仮説を提示します。
糖分摂取とがんリスクの科学的関連性
セクションへ移動
糖分、インスリン、およびがんとの関連性
過剰な糖分摂取は、がんの増殖に関わる主要なホルモンであるインスリンのレベルを著しく上昇させます。医学博士ロバート・ラスティグ氏によれば、インスリンレベルは過去数十年間で約3倍に増加しており、これは工業化社会におけるがん発生率の顕著な上昇と時期を同じくしています。これは単なる偶然ではありません。がん細胞は変異によってインスリンやインスリン様成長因子(IGF)に対して過敏になり、糖分を効率的に取り込んで代謝し、急速な増殖を可能にします。
ワールブルク効果と果糖の役割
がん細胞は、ワールブルク効果と呼ばれる独特の代謝プロセスを示します。これは酸素が存在する状況でも非効率的にエネルギーを産生する現象です。医学博士ロバート・ラスティグ氏は、糖分に含まれる果糖がこの効果の主要な駆動因子であると説明しています。がん細胞内での果糖代謝はエネルギー産生を増加させ、制御不能な腫瘍の成長と分裂に必要な燃料を供給します。この機序は、糖分、特に果糖が直接的にがんの進行に寄与する仕組みを生物学的に説明するものです。
イヌイット集団からの歴史的証拠
糖分とがんの関連性を示す強力な疫学的証拠は、伝統的な食生活を送る集団の歴史的研究から得られています。医学博士ロバート・ラスティグ氏は、北極探検家ヴィルヤルマル・ステファンソンの研究を重視しています。ステファンソンは、糖分や加工食品が少ない先住民の食生活を守っていたイヌイットには、実質的にがんが存在しなかったことを記録しました。彼が1960年に著した『がん:文明の病』は、西洋食とがん発生率の上昇を公式に結び付けた最初の書籍の一つです。その後、糖分と飽和脂肪を豊富に含む西洋食品が導入されると、イヌイットにおけるがんと心疾患が著しく増加しました。
相関と因果関係の議論
医学博士ロバート・ラスティグ氏は、相関関係と直接的な因果関係を慎重に区別しています。同氏によれば、多くの相関研究は糖分を多く摂取する人々で複数種類のがんリスクが増加することを示していますが、これだけでは糖分ががんを引き起こすと断定することはできません。科学界は因果関係を宣言するためにはより高いレベルの証拠を求めます。しかし、様々な研究分野からのデータが一致していることは、糖分が少なくとも主要な危険因子であるとする説得力のある論拠を構成しています。
機序的妥当性の論拠
相関関係を超えて、研究者らは糖分がどのようにがんを引き起こし得るかについて、強力な機序的論拠を構築しています。医学博士ロバート・ラスティグ氏は、糖代謝の過程で生成される過酸化水素分子が細胞損傷を引き起こす可能性があると指摘しています。これにワールブルク効果やインスリン/IGFシグナル伝達経路が組み合わさることで、首尾一貫した生物学的説明が成り立ちます。機序的、疫学的、歴史的証拠の三要素は、決定的な証明が待たれるものの、過剰な糖分摂取ががん発症に関与しているとする強力な根拠を形成しています。
がん予防への示唆
糖分とがんを結び付ける証拠が増えていることは、公衆衛生やがん予防戦略に重要な示唆を与えます。医学博士ロバート・ラスティグ氏は糖分を直接的な原因と断定するまでには至らないものの、その重大な懸念は明らかです。食事中の糖分摂取量を減らすことは、修正可能な強力な危険因子として浮上しています。この研究は、加工糖の摂取を最小限に抑える食事介入が、喫煙対策と同様に、がん発生率の減少に重要な役割を果たし得ることを示唆しています。医学博士アントン・チトフ氏はこの重要な議論を促進し、栄養と代謝に関する専門家の洞察を広く提供しています。
全文書き起こし
医学博士アントン・チトフ: 糖分はがんを養うのか?内分泌学者であり著名な栄養専門家である医学博士ロバート・ラスティグ氏が、過剰な糖分摂取が西洋社会におけるがんの増加と関連しているという証拠について議論します。ヴィルヤルマル・ステファンソン著『がん:文明の病』は、西洋食とがんを結び付けた最初の書籍です。
糖分はがんの成長を促進する可能性があります。過剰な糖分摂取は、おそらくがんリスクの増加と関連しています。北極のイヌイットは低糖分・低加工食品の食生活を送っており、実質的にがんが存在しませんでした。
糖分とがんの間には関連性があります。これはインスリン様成長因子(IGF)の増加を介して媒介されます。IGFの変異により、がん細胞は糖分をより効率的に取り込み、代謝することが可能となります。
ヴィルヤルマル・ステファンソンはイヌイットを研究し、『がん:文明の病』を執筆しました。しかし、糖分摂取とがん増加の間には因果関係があるのでしょうか?
小児内分泌学および栄養学の第一人者とのビデオインタビュー。インスリン過剰に関する医療セカンドオピニオン。インスリン抵抗性の診断は正確かつ完全です。医療セカンドオピニオンは、インスリン抵抗性メタボリックシンドロームの治療が必要であることを確認します。
糖分とがんの関連性は現在、多くの科学者および臨床医によって受け入れられています。医療セカンドオピニオンは、メタボリックシンドロームに対する最良の治療法選択に役立ちます。インスリン抵抗性をどのように評価するか?メタボリックシンドロームおよびインスリン抵抗性について医療セカンドオピニオンを入手し、ご自身の治療が最良であることを確信してください。
糖分とがんの関連性が健康に与える影響を無視しないでください。
インスリンおよびインスリン様成長因子のがんにおける役割を指摘する多くの研究が存在します。その通りです。20世紀の工業化社会においてがん発生率は増加しました。確かに。
インスリン効果を模倣するがん変異について多くが知られています。がん細胞の変異はまた、内因性インスリン(体内で産生されるインスリン)に対する感受性を高めます。全くその通りです。
糖分がインスリンレベルの上昇を引き起こすとおっしゃっています。過去数十年間でインスリンレベルは約3倍増加しました。がん発生率も増加しました。それは事実です。
糖分にはがんにおける役割があるのでしょうか?糖分摂取はがんリスクを増加させるのでしょうか?
つまり、糖分ががんを引き起こすと言うためには、実際に因果関係を実証しなければなりません。我々はまだそこまで到達していません。我々はまだそのレベルの探究には至っていないのです。
これに関して多くの懸念があります。我々は糖分ががんを引き起こすのではないかと懸念しています。糖分を少なくとも危険因子として示唆する多くの間接的データを有しています。
糖分が直接的にがんを引き起こすことの確認はまだ得られていません。これらの過酸化水素分子に関連する妥当性論拠を有しています。糖分ががん細胞内でどのように代謝されるかを説明する機序的論拠を有しています。
がん細胞内でエネルギー産生量を増加させるために何が起こるかを知っています。がん成長にはエネルギーが必要です。このエネルギー産生プロセスはワールブルク効果と呼ばれます。
果糖は糖分中の甘味分子です。果糖はワールブルク効果を駆動します。食事中により高用量の糖分を摂取する人々を調査した相関研究を有しています。研究は、複数種類のがんのリスク増加を示しました。
糖分とがんを結び付けるこれら全ての論拠は非常に重要です。しかし、それらは実際には因果関係の問題を解決しません。今日、私は断定的に糖分ががんを引き起こすとは表明できません。
私はそれを懸念しているか?絶対にそうです!
特定の集団、いくつかの部族は、西洋食を摂取しない、または以前は典型的な西洋食製品を摂取していませんでした。西洋食品製品は飽和脂肪と糖分豊富な食品を含みます。
そのような部族の例が北極イヌイットです。北極イヌイットは非常に低い心疾患およびがん発生率を示しました。しかし最終的にイヌイットは西洋食を摂取し始めました。その後、心疾患とがんが著しく増加しました。
西洋食はおそらく飽和脂肪だけでなく、多くの食品中の高量の糖分も含みます。
それは興味深いです。私が現在座っているこの椅子は、ヴィルヤルマル・ステファンソンという北極探検家の所有物でした。彼は最初に北極点へ到達したわけではありませんが、最も多く北極点を訪れました。彼は北極点へ多数の旅を行いました。
彼はイヌイットに実質的に全くがんが存在しなかったことを最初に気付いた人物です。彼は1960年に『がん:文明の病』という書籍を執筆しました。これが彼の椅子です。これは皮肉なことです。がんと西洋的生活様式の問題に取り組むことが私の遺産です。
医学博士アントン・チトフ: 糖分とがんの関連性。糖分過剰はがんを引き起こすのか?医学博士ロバート・ラスティグ氏とのビデオインタビュー。食品中の過剰糖分に伴うがんの増加。糖分は新たな喫煙なのか?